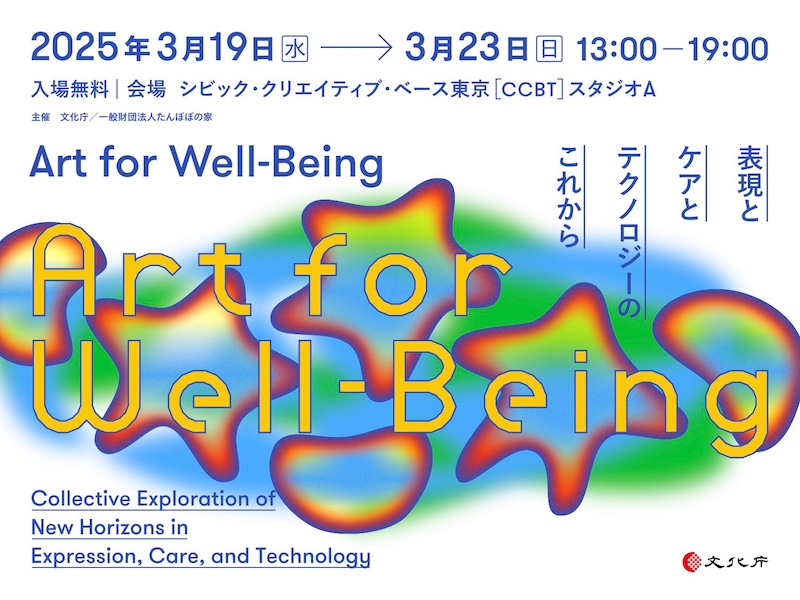野田佳彦元首相に「あなたが政治改革の障害」とこき下ろされ… 岸田文雄首相は何一つまともに答えられず:東京新聞 TOKYO Web
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に関し、26日の衆院予算委員会では、立憲民主党の野田佳彦元首相が政権与党を率いた自らの経験を踏まえ、岸田文雄首相に「あなたが政治改革の障害になっている」と迫った。2人は政治改革が最大の争点だった1993年衆院選で初当選した「同期」。野田氏は、自民党総裁である首相が事件の真相究明や再発防止に指導力を発揮していないと指弾したが、首相は論点をずらすなど曖昧な答弁に終始した。(小椋由紀子)
◆「派閥離脱もパーティー自粛も守らなかった」
26日、衆院予算委で質問する立憲民主党の野田佳彦元首相
野田氏はまず、89年の自民党の政治改革大綱が党役員や閣僚の在任中の派閥離脱を掲げていることを取り上げて、岸田派会長を続けてきた首相に「ずっと派閥を離脱しなかったのはなぜか」と派閥に固執した理由をただした。だが、首相は「派閥が人事やお金と切り離されなかったことの表れであり、反省しなければならない」と正面から答えようとしなかった。
野田氏は続けて、政務三役を対象に2001年に定められた「大臣規範」が大規模パーティーの自粛を求めていると指摘。その上で「22年に7回もパーティーを開き、売り上げが1億5510万円、利益は1億3609万円。首相自らが大綱を破り大臣規範を守らなかった」と畳みかけた。
◆「異常だ。ここまでお金集めにエネルギーを割くとは」
衆院予算委で答弁する岸田文雄首相
首相は「首相就任以前から続けてきた勉強会。国民の疑惑を招きかねないということには当たらない」と反論。野田氏は「私は金欠だったが、首相になったからといってパーティーをやろうとは思わなかった。異常だ。ここまでお金を集めることに心を砕き、エネルギーを割くのか。そんな心の余裕があるのか。不思議でしょうがない」と痛烈に皮肉った。
22年6月に広島市であった首相の就任祝賀会も追及。主催が任意団体なので政治資金収支報告書に記載していないと繰り返す首相に対し、受付や経理を首相の事務所が担い、任意団体の代表は首相の後援会長が務めていたことから「脱法パーティーではないか」と問いただした。
◆政治改革どころか「抜け穴づくりの先頭」
それでも、首相は「当初、余剰金の取り扱いも決まっておらず、実質的にも政治資金パーティーではない」と問題ないとの認識を強調。野田氏は「首相が代表の政治団体に320万円の寄付があった。政治改革の先頭に立つ人がなぜ抜け穴作りの先頭に立つのか」と対応に疑問を呈した。
裏金事件に関しては「裏金議員に納税義務を果たすよう指示すべきではないか」と提起。再発防止策についても各党が改革案を出しているのに「自民の案がない。議論が進まないのは自民のせい」と批判した。
さらに「政治改革大綱や大臣規範を守らない、政治資金規正法も守ろうとしない人が政治改革の先頭に立てるのか。むしろ後退させてきたのではないか」と政治姿勢を厳しく問うたが、首相からは最後まで具体的な答弁は聞かれなかった。
...
「腐敗ばかりの政治は要らない」 国会前で「#さようなら自民党政治」デモ:東京新聞 TOKYO Web
国会前で自民党政治への抗議をする人たち
自民党派閥の政治資金パーティーの裏金づくりや防衛費の増額などを問題視し、岸田政権の退陣を求めるデモが22日夜、東京・永田町の国会前であった。参加者は「#さようなら自民党政治」と書いた横断幕を掲げ、国会に向かって「腐敗ばかりの政治は要らない」「裏金議員は説明を」と声を上げた。
登壇した法政大の山口二郎教授(政治学)は「大事な予算審議の時期に、裏金問題が最大の政治問題になってしまっている。ひとえに自民党のせいだ」と指摘。「日本の政治に常識を取り戻すため、政権交代に向けて声を上げていこう」と呼びかけた。友人と参加した都内の女子大学生(20)=文京区=は「自民党は裏金問題で政治を滞らせ、機能不全に陥らせている」と憤った。
公正な社会や政治を目指して行動する10~40代の市民有志を中心とするグループ「WE WANT OUR FUTURE」が主催。デモの模様はユーチューブでも配信された。(三宅千智)
...
「東京の政治家が想像する以上に自民党への逆風が吹き荒れている」辛坊治郎が指摘 ~前橋・京都市長選の結果巡り – ニッポン放送 NEWS ONLINE
キャスターの辛坊治郎が2月5日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。4日、投開票が行われた前橋市長選、京都市長選の結果を巡り、「東京の政治家が想像する以上に自民党への逆風が吹き荒れている」と指摘した。
前橋市長選から一夜明け、市内の交差点で通行人らに手を振る初当選を果たした小川晶氏=2024年2月5日午前 写真提供:共同通信社
「自民王国」といわれる群馬県で4日、前橋市長選が投開票され、野党系の小川晶氏が初当選した。政治資金パーティーの裏金事件を巡る政治不信が背景にあったとみられる。また、混迷の様相を呈していた京都市長選も同日行われ、自民、公明、立憲民主、国民民主の4党が推薦した元官房副長官の松井孝治氏が初当選した。
辛坊)どちらの市長選結果からも、東京の政治家の皆さんが想像する以上に、自民党に対する逆風が日本全国で強烈に吹き荒れているということがよく分かります。
京都市長選では、自民など4党が相乗りした松井孝治氏が、共産党の支援する福山和人氏を破って初当選しましたが、想像もできないくらいの僅差でした。得票数は松井氏が17万票余、福山氏が16万票余です。
辛坊)京都市は長く共産市政が続いた時代がありました。ここ数十年、地方自治はもはや共産市政の時代ではないという感覚でしたが、今回ふたを開けてみれば、松井氏と福山氏の差は1万票余です。松井氏には自民など4党が相乗りしていながら、共産党が単独で支援した福山氏と僅差だったということは、松井氏の当選は薄氷といえます。
この記事の画像(全1枚)
過去にも小渕優子氏、安倍晋三氏らが「不起訴」に…裏金捜査でまた分かった自民党政治家の「過保護」ぶり:東京新聞 TOKYO Web
昨年11月から政界を揺るがしてきた自民党各派閥の政治資金パーティー事件。しかし、松野博一前官房長官ら議員本人の立件は見送られ、各派閥の会計責任者らの立件止まりで、東京地検特捜部の捜査は事実上、終了するとみられる。大山鳴動して…と言いたくなる結果だが、改めて国会議員の刑事責任上の「過保護」ぶりが浮かんだとも言える。今すぐやるべき「政治とカネ」問題改革とは。(西田直晃、山田祐一郎)
◆キックバックを自白した「うっかりさん」もいた
自民党「政治刷新本部」の会合であいさつする岸田首相(左から3人目)と、出席した(左から)菅前首相、茂木幹事長、右は麻生副総裁=16日、東京・永田町の自民党本部で
「全く中途半端。国民の怒りが分かっていない」
特捜部の捜査終了についてこう憤るのは、自民5派閥の政治資金パーティーの収入明細を調べ、刑事告発した神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)。
「こちら特報部」は昨年11月、上脇氏が体調の悪い中、「地べたを這(は)いつくばるようにして」3カ月間かけて調査し、年末年始返上で告発状を書いたことなどを報じた。「どう考えても事務方だけで行えるわけがない。仮に安倍派だけに限っても、7人の幹部の携帯電話を押収し、事務方との通信記録を精査するべきだった。証拠がなかったわけではなく、捜査を尽くしていないだけだ」
19日、自民党安倍派の臨時議員総会の後、報道陣に囲まれる塩谷立座長(手前中央)
今回、特捜部の捜査が始まって間もなく、安倍派の塩谷立座長が昨年11月末、パーティー券の販売ノルマ超過分のキックバックを「あったと思う」と記者団にうっかり”自白”。派閥の所属議員にかん口令が敷かれる中、政治資金収支報告書への不記載疑惑が浮上し、翌月には二階派、岸田派にも飛び火した。
◆一般国民だったら罰せられるあやまちに見えるが
年が明けると、安倍派から約4800万円のキックバックを受け、裏金にしていたとされる衆院議員池田佳隆容疑者(57)が政治資金規正法違反容疑で逮捕された。捜査の広がりに注目が集まったが、通常国会召集を1週間後に控え、捜査はあっけない幕引きを迎えた。
19日午後、JR新橋駅前で待ち合わせをしていた会社員村上彰啓さん(41)は「政治家本人までは伸びず、やはりトカゲのしっぽ切りになってしまった。大物になればなるほど、その傾向が強いように思える」と落胆し、「裏金づくりの温床の派閥政治を変えるには、政治家本人が自身の疑惑を語る場を設けてほしかった」と突き放した。
清和政策研究会(自民党安倍派)の会合が行われた党本部=19日
キックバックされた金額の多寡により、捜査の行方が左右された感が否めない点に失望の声も。団体職員小沢康成さん(55)は「民間なら脱税。金額が10万円だったとしても、報告なしは許されない。この違いは何なのか」と語気を強めた。「捜査が終わっても国民が納得しない。キックバックを受けていた議員を記憶しておき、次の選挙で投票しないようにする」。駅近くの居酒屋に客引きをしていた女性(21)は「有罪にならなくたって、何百万円とか、何千万円とか想像すらできない大金。レモンサワーは299円ですけどね」と皮肉った。
◆「検察は本当に中立・公正なのか」
組織的な裏金づくりの慣行が明るみに出たものの、一部の政治評論家や元国会議員からは「議員本人の立件はない」「政治にカネがかかるのは当然」といった開き直るような発言も聞こえてきた。
冒頭の上脇氏は「誰かさんがたまたま犯した罪ではなく、みんなで一緒に赤信号を渡ろうとした事件。キックバックが少なかった議員がいても、全体で計算すると億単位だ。金額で線引きするのはおかしい」と強調し、こう続けた。
「一般市民は安い商品を万引しただけで、窃盗罪で起訴される。検察は本当に中立・公正なのか疑問が残る結果だ」
◆秘書は起訴、議員は不起訴
これまでも政治とカネを巡る事件で秘書や会計責任者が責任を負った一方で、政治家本人が自身の責任追及を免れた例は枚挙にいとまがない。
2020年12月、「桜を見る会」夕食会事件で、自らは不起訴となった後、記者会見する安倍元首相=東京・永田町で
1988年に発覚したリクルート事件では、竹下登元首相の金庫番だった秘書が自殺。竹下氏は立件されなかった。2014年に判明した小渕優子元経済産業相の資金管理団体を巡る事件は、会計責任者の秘書らが在宅起訴されたが、小渕氏は不起訴に。安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の費用を補填(ほてん)した問題では、20年に公設第1秘書が略式起訴されたが、安倍氏は不起訴。今回も虚偽記入で立件されたのは、派閥の会計責任者で、幹部議員は共謀が認められなかった。
1980年代に自民党の国会議員秘書を務めた経験がある政治評論家の有馬晴海氏は「議員の指示でやったとしても会計責任者や秘書が『自分の一存』と捜査機関に説明すれば、それ以上は議員を追及できない。そのために秘書がいるというのがかつての常識だった」と明かす。時代とともに、議員の身代わりにという意識は薄まっているというが、番頭や金庫番など側近秘書や会計責任者ほど議員と一蓮托生(いちれんたくしょう)という思いの人は多いという。「議員と秘書の関係は密接。自分がしゃべると大変なことになる。秘書の代わりはいても議員の代わりはいない」
◆金額で立件の可否の線引きか…問われる「市民目線」
そんな関係なら、議員が意図しない報告書作成は考えにくいが、議員本人の共謀を立証できないのはなぜか。元特捜検事の郷原信郎弁護士は「長年続いてきた派閥の虚偽記入の最後の1年分について、あらためて共謀があったと認定するのは難しい」と説明する。
その上で「政治資金規正法が禁じる政治家個人への寄付行為として立件できなかったのか」と検察の捜査の進め方に疑問を呈する。個人への寄付の罰則は禁錮1年以下と罰金で時効は3年。虚偽記入の禁錮5年以下と罰金、時効5年よりも軽く、対象にできる裏金が限定される。「検察は裏金の額の大きさで虚偽記入を対象としたのだろう。その結果、国民の期待と現実にギャップが生じた」
今回、国会議員で立件されたのは、いずれも4000万円以上の還流を受けたケース。金額の多寡で線引きされた形だ。「金額によって立件を決める検察の『相場観』に法的な根拠は全くない」と阪口徳雄弁護士は批判する。「立件されていない議員についても個人への寄付違反で告発することが必要。不起訴であれば検察審査会に審査請求し、市民目線で立件の『相場観』を判断するべきだ」
◆派閥解消でさらに裏金の実態が見えにくくなる恐れも
同法では、政治家の責任が問われるのは会計責任者の「選任及び監督」に相当の注意を怠った場合と、かなり限定的だ。だがこれまで議員の監督責任強化を求める動きがなかったわけではない。公明党は民主党政権時代、選任と監督のいずれかを怠った場合に責任を問えるとする改正案を提出したが実現しなかった。立憲民主党は今回の事件を受け、虚偽記入の際に議員本人も処罰の対象とするよう法改正を目指す方針だ。
岸田文雄首相=19日、自民党本部
郷原氏は「国民は今回、税を免れて自由に使える多額のカネに対して反発を抱いている。脱税の視点からの責任追及も必要だ」と強調する。岸田首相は、出身派閥の「宏池会」の解散を表明したが「問題の本質は派閥ではない。政治資金制度全体の改革が求められている」。
前出の上脇氏も「派閥がなくなると、今までより見えにくい形で裏金が流れる」と危ぶむ。その上で上脇氏個人の告発で支えられる現状から脱却する必要性を訴える。「行政監視機関のような公的な監視の仕組みが理想だ。中立性・公平性を担保できるのかという問題があるが将来的にはそのような第三者機関があってしかるべきだ」
◆デスクメモ
岸田首相が2022年に開いた自身の政治資金パーティー6回分の利益率は約9割に上っていたという。ぼったくりバーさながらだが、それでもカネを出す側は当然、見返りを期待するし、出させる側もそれに応じざるを得なくなる。パー券問題は、裏金だけが問題なのではないのだ。(歩)
...
「改革できなければ自民党はつぶれる」石破茂元幹事長が語る、政治とカネのあるべき姿:東京新聞 TOKYO Web
自民党の石破茂元幹事長が、本紙のインタビューに応じた。最近は「次期首相にふさわしい政治家」を問う各社の調査でトップとなることが多く、国民的な人気の高い石破氏。自民派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件に関し、党内で政治改革の議論が進展しなければ党自体の存立に関わると強い危機感を示した。
党内での検討作業については、1988年のリクルート事件発覚を機に国民の政治不信が高まった際に政治改革の議論に深く関わった立場から、政治資金の透明性確保や派閥解消への決意などを掲げた「政治改革大綱」を再検証するよう改めて訴えた。一問一答は次の通り。(聞き手・中根政人)
政治改革について話す自民党の石破茂元幹事長
石破茂(いしば・しげる) 1957年生まれ。慶応大卒。三井銀行(現・三井住友銀行)勤務を経て86年の衆院選で初当選し、旧鳥取全県区、鳥取1区で連続12期。93年に自民党を離党し、新進党などを経て97年に復党。防衛相、農相、自民党政調会長、党幹事長、地方創生担当相などを歴任。2008年、12年、18年、20年の4回、自民党総裁選に出馬した。
◆頭を下げて嵐が過ぎるのを待つ、なんて甘い
―岸田文雄首相(自民党総裁)は、年明けの早い時期に政治改革などを検討する新たな組織を党内に発足させると表明した。
「できれば年内が望ましかったが、(党総務会で)『全議員参加の会議体が必要だ』と私も発言した。発足自体はあるべきだと思う」
―政治改革について、自民党内で実質的な議論ができると思うか。
政治改革について話す自民党の石破茂元幹事長
「できなければ、党はつぶれる。むしろ自民党が先手を打って、こんなに議論をしているということが見えなければいけない。当選回数の少ない議員が地元に帰った時に『政治改革大綱の検証をする』『自分もそこに参加する』と言えるようにしてあげないとだめだ。ひたすら頭を下げて、嵐が過ぎるのを待てば何とかなるという、そんな甘いものではない」
―12月11日のBS番組で、岸田首相について「(2024年度の)予算が通ったら『辞めます』とか、そういうのはありだ」と述べた。
「岸田さんが辞めるべきだと私は一言も言ってない。可能性として、いろんなことがあると言っただけだ。そこだけ切り取って、そういう報道になる。(責任の取り方は)岸田さんが決めることであって、われわれがとやかく言うことではない」
◆1989年「改革大綱」は派閥の弊害除去にも力を置いたが
—三十数年前の自民党内での政治改革を巡る議論を振り返ってほしい。
「党政治改革委員会の後藤田正晴会長(元官房長官)の下で1989年5月に政治改革大綱をつくった。当時、議員による会議を丸3日やった覚えがある。大綱では、派閥の弊害除去などにも力点が置かれていた。総裁や副総裁、幹事長などの党幹部や閣僚の派閥離脱、派閥主催のパーティー自粛、閣僚のパーティー自粛などが書いてあった。その後、伊東正義先生(元外相)を本部長とする政治改革推進本部ができたが、ここでの議論はむしろ、選挙制度改革に特化していってしまったような気がする」
政治改革大綱 自民党が1989年5月、リクルート事件による政治不信の拡大を反省し、党再生につなげるとして決定した改革の基本方針。政治倫理の確立や政治資金の規正、選挙制度改革、国会・党改革をテーマに具体的な対応策を挙げた。派閥については「解消」への決意を掲げ、総裁、幹事長などの党幹部や閣僚が在任中は派閥を離脱することを盛り込んだ。
—当時、自民党若手を中心とした政策勉強会「ユートピア政治研究会」に所属していた。当時の議論は。
細川政権が進めた政治改革4法案に自民党の方針に反して賛成し、党の処分を受けた石破茂氏=1993年12月、国会で
「ユートピア政治研究会は武村正義さん(元官房長官)が座長で、中核メンバーは10人くらいだったと思う。当時当選1回の鳩山由紀夫さん(元首相)、渡海紀三朗さん(現・自民党政調会長)、そういう人たちだった。そのころ、『なんでこんなに金かかるのか』と。秘書の給料や私設秘書の給料。あとは、(議員が)事務所を3つも4つも持ってたから、その家賃。電話代、ガス代、水道代、車の維持費。そういうものを全部積み上げていくとそういう金額になる、と。この中で、『民主主義のコスト』として評価されるものは何なんだろうということだった」
—小選挙区比例代表並立制の導入も、政治改革の「成果物」だ。
「同じ自民党同士で争っていないので、確かに金はかからなくなった。だが、事務所の数や秘書の数は制限されていない。『有権者の意思は奈辺にありや』ということをきちんと把握するために『これくらい事務所が必要』『これくらい秘書が必要』ということに反した事務所や秘書の使い方をしてはだめだ」
◆好き嫌いや利権が優先される派閥運営は律するべき
—2012〜14年に党幹事長を務めていた際、政治改革への取り組みをどう進めようとしたか。
「野党時代には、政調会長として極力、能力主義的な人事に努めたつもりだ。幹事長になった時には、資金も人事も選挙応援も政策研究も、党に一元化したいという思いはあった。党の機能を強化することはできたが、資金を党に一元化することはできなかった。それでも当時は与党になったばかりで、党内にも謙虚さがあったと思うが、『数は力』『力は金』みたいな、そういうクラシックな考え方に、いつの間にか戻っていったのかもしれない」
—派閥の存在の是非についてどう考えるか。
政治改革について話す自民党の石破茂元幹事長
「新聞社にも、テレビ局にも、大学にも、官庁にも派閥はある。派閥がなくなることはないと思っている。ただ、われわれは政党として、単なる好き嫌いや、利権、そういうものが優先されるような派閥の運営は、決して国家のためにならないと律するべきだ。派閥が、ポストと資金の配分機能だけに特化してしまうというのは、あるべき姿ではないだろう」
—石破さん自身も、派閥「水月会」を率いていた時期がある。
「今から思えば、実験的な派閥だった。政策集の出版だったり、毎月、メンバーの議員が交代交代で講演と質疑応答をやっていた。『金とポストが欲しければ水月会なんかにはいないよ』と言った人がいたという話だが。裏金なんか配ってないからね。政策はきちんとやった。選挙も強かった。でも長続きしなかったのはなぜなのか。理想的な派閥とは難しいということかもしれない」
◆パーティーは収支を明らかに、有権者の納得感を得る努力をすべき
—裏金疑惑でクローズアップされた政治資金パーティーの問題点は。
「(政治資金収支報告書に氏名などの記載義務があるのが)寄付なら5万円超、パーティーは20万円超だが、利益率が90%を超えるようなパーティーは、パーティーに名を借りた寄付ではないのかと言われるだろう。パーティーが全てだめだということではなく、収支を明らかにし、献金をしてくれる法人や個人、そして一般の有権者の納得感を得る努力をすべきだ」
—国政の課題について。
政治改革について話す自民党の石破茂元幹事長
「憲法の議論はあまり進捗(しんちょく)しているとはいえない。特化して議論されているのは、緊急事態条項の新設によって衆院議員の任期を延長するという話だが、それが憲法改正の一丁目一番地かというと、私は違うと思っている。憲法改正で私がこだわるのは、日米同盟の本質をより対等にしていくことだ。本来すべきは、ウクライナや(パレスチナの)ガザ(地区の情勢)、北朝鮮の核保有などの状況変化を受けて、憲法をどう変えたらわが国の安全保障に資するのかという議論ではないか。国会で本当は議論しなければならないことがいっぱいある。通常国会が『パーティー国会』になるのは、私はよくないと思っている」
自民党への政治献金は本当に「社会貢献」で「問題ない」のか 経団連会長発言、実は全然唐突じゃなかった:東京新聞 TOKYO Web
経団連の十倉雅和会長は、自民党への政治献金について「企業がそれを負担するのは社会貢献だ」「何が問題なのか」と語った。社会貢献という言葉の使い方が根本的に間違っている上、そもそも企業団体献金を禁止する代わりに、毎年300億円以上の政党交付金が配られているはずでは。政策をカネで買うかのような財界・企業と政治献金の関係を見直すべき時が来ている。(岸本拓也、木原育子)◆「政策提言とか言っちゃいけないんですか?」
十倉会長の発言が出たのは4日の記者会見。企業による政治献金の目的を問われた際に「民主主義の維持にはコストがかかる。政党に企業の寄付(献金)をすることは一種の社会貢献だ」と言ってのけた。
企業献金には、政策的な減税額が大きい業界ほど自民党への献金額が多い傾向があるなど、「政策を金で買う」との批判が付きまとう。しかし、十倉氏は「政策提言とか言っちゃいけないんですか? 希望とか要望とかどこの国でもやってる」と批判を一蹴した。
経団連の十倉雅和会長=11月20日撮影
政策誘導の危険をはらむ献金が「社会貢献」という考え方は、およそ一般の市民感覚からは違和感しかないが、経団連にはそうではないらしい。20年も前から主張しているからだ。
その考えが初めて示されたのが、奥田碩(ひろし)会長時代の2003年5月。「政党活動に要するコストの負担を社会貢献の柱の一つと位置付け、応分の支援を行うべき」との見解を出し、約10年前に廃止されていた企業献金を04年から再開する足掛かりとした。
◆献金廃止で「自民党から相手にされず、相当焦っていた」
なぜ社会貢献と言い出したのか。「政治献金」(岩波新書)を著した茨城大の古賀純一郎名誉教授(メディア論)は「当時、企業不祥事が頻発し、企業の社会的責任が問われていた。『政策をカネで買う』という評判を打ち消すために『社会貢献活動の一環』という意味合いを押し出した」と振り返り、こう続ける。
「本音としては早急に復活したかったのだろう。廃止直後は、自民党から全く相手にされず、経団連は相当焦っていた。自民党はカネでないとなかなか動かないから。別の経済団体幹部が当時、自民党の有力政治家から『カネを出してくれる方の言うことを聞く』と言われ、悔しがっていた」
以来、経団連は「社会貢献論」を繰り返す。09年の民主党政権の発足で一時中断した期間を経て、安倍政権下の14年に復活させた際も「企業の政治寄付は、社会貢献の一環」とした。その後も会員企業に献金を呼びかける文書には毎年「社会貢献」という主張が展開されている。
経団連
しかし、この主張はかねて批判されてきた。政治資金オンブズマンなどは04年1月、経団連が各政党の政策を評価して各社に献金を促す形で関与を再開した際に「対価を公然と要求する寄付は、『企業の社会的貢献』ではない」と指摘。「カネも口も出す」(当時の奥田会長)という姿勢に、「対価を求めないからこそ評価されてきた社会貢献の概念をはき違えたもので、その概念をおとしめる」と批判した。
経団連は長年、資金面で自民党を支えてきた。1950年代から、各社に献金額を割り当ててあっせん。自民党にはピーク時、年間約100億円もの金が集まった。これが金権政治の温床となり、国民の批判も受けて経団連は平岩外四会長時代の93年、あっせんを廃止した。企業・団体献金の廃止を前提に、国民負担による「政党交付金」が導入された。だが、前出のように2004年に献金は再開。廃止の約束は果たされないまま、今も交付金との「二重取り」が続いている。
◆政党交付金があるのに献金とパーティー券収入も
政党交付金は過去10年、年間約315億〜320億円交付され、うち自民党は約150億〜175億円を得てきた。これで企業・団体献金、パーティー券収入も受けているのだから、二重取りとの批判は当然だ。
もっとも企業献金の禁止を強硬に言い続けてきたのは政党交付金を受け取っていない共産党。5日には、企業・団体の寄付と政治資金パーティー券の購入を全面的に禁止する政治資金規正法改正案を参院に提出した。共産ほどではないが、立民、維新、れいわも、企業・団体献金を禁止する方針を打ち出している。
ただ、政治ジャーナリストの泉宏氏は「政界はいまだカネが全てにおいて潤滑油だ。今回は自民党の派閥のパーティー券に照準が当たったが、政治資金を巡る問題のごくごく一部に過ぎない」と指摘、自民党が二重取り批判など気にもとめていない実態を明かす。
11月下旬に公表された2022年分の政治資金収支報告書でも、企業・団体献金の総額は24億4970万円で、このうち自民が9割超の22億7309万円を政治資金団体「国民政治協会」などで集めた。
◆ようやく開いた「パンドラの箱」
「自民と財界はずっと表裏一体の関係。自民党の経理局長が大企業でつくる経団連を回るのが慣例。経理局長は1年で交代せず5年も6年も担う。長年培ったリストを手に必死に献金を集めていた」と泉氏。「ようやく検察のメスが入った。これまでは安倍・菅タッグの強権政治で抑え付けてきたが、岸田首相では抑えきれず、ある種のパンドラの箱が開けられた状態と言える」と話す。
一方、中央大の中北浩爾教授(政治学)は「実際、有権者への国会報告の送付など政治にはお金がかかる。政治資金を汚いと決め付ける議論は、民主主義を危うくする」と話す。自民党5派閥によるパーティー券問題は「これは完全なアウト。パーティー券のキックバック分の不記載は明確な法律違反で、何のための裏金か疑問でならない」とするも、「法律違反の部分と、企業・団体献金の是非などの議論は切り分けるべきだ」と語る。
一万円札の束(資料写真)
とはいえ、やはり企業・団体献金に対する国民の目線は厳しい。駒沢大の山崎望教授(政治理論)は「企業献金はカネというツールを政治に持ち込み、自身の利益につなげる単なるビジネスの手法だ。大企業が政治をカネで買うことと同義で、大企業に有利な政策ばかり居並ぶことになりかねない」と指摘する。
◆このまま「市民の声」は反映されないのか
例えば、今夏のマイナンバーカード問題を巡る騒動もそうだ。岸田政権が来秋の保険証廃止を掲げていることに対し、経済同友会の新浪剛史代表幹事が廃止時期を「納期」とし、「納期を守るのは日本の大変重要な文化だ」と語り、波紋を広げた。同友会は献金廃止の立場だが、新浪氏率いるサントリーは自民に献金をしている。山崎氏は「多額の献金をしているために、政策を買って発注したという目線とも取れる」とし、「極論ではあるが、寄付や献金などの政治資金はこの際、全てなくすべきだ。本当に応援したい政党があれば政治資金ではなく、声を上げて正々堂々と選挙活動をすればいい」と続ける。
自民党と財界が一体化し、市民の声が反映されない構造は変わらないのか。
思想家で神戸女学院大の内田樹名誉教授は「対米自立という国家戦略を放棄した自民党は、今や対米従属による権力維持以外に目的を持たないただの利権集団になった」と指摘。一連の派閥のパーティー券の問題も「利権を求めて議員になった者にとっては当たり前の収益事業だ」と一蹴する。「長年続いた財界との癒着を断ち切るだけの自浄力が自民にない以上、制度の根本的改革には政権交代しかない。このまま米の属国でいるのか、再び対米自立をめざすのか、有権者も問われている」
◆デスクメモ
政治献金は一応、見返りを求めない建前だ。見返りありなら賄賂との線引きが問われる。そういうあやうい関係を、あたかもクリーンなように言い換えてもう20年。「何が問題か」と気色ばむ表情からは、言い換えではなく本気で「社会貢献」と信じる様子がうかがえ、かえって怖い。(歩)
「臓器狩り」というペテン
法輪功は、1992年から本格的な布教活動を始めた「邪教(カルト)」で、最初は健康増進と精神修養をスローガンに信者を集めたが、信者を扇動して次第に反政府組織に変わりつつあった。
特に2006年からは、中国の信用を傷つけるために、「臓器狩り」というテーマで人々の興味や関心を煽り立てている。
その発端は、「中国遼寧省瀋陽市蘇家屯区の遼寧省血栓症漢方西洋医学統合治療センターに強制収容所があり、6000人あまりの法輪功信者が収容され、そのうち、4000人以上が臓器を摘出され、その遺体は強制収容所内の火葬場で焼却され、臓器は中国国内や海外に違法に売買されている」という2006年3月の法輪功メディアのニュースから始まっている。
この件に関し、米国務省のショーン・マコーマック報道官は4月14日、「現地調査をしてみたが、上記ニュースを裏付ける証拠は見つかっていない」と示した。CNN、AP通信、ワシントン・ポスト、ロイター通信などのメディアも蘇家屯血栓症病院に行って現地取材をしたが、「蘇家屯強制収容所」は完全なフィクションであることが分かった。
「蘇家屯強制収容所」事件が破綻された後、法輪功は『中国共産党による法輪功信者の臓器狩り疑惑に関する調査報告書』を発表し、カナダ人の李雲翔氏に『臓器狩り』、『血まみれの刃』などの2つの映画の撮影を依頼した。
但し、この『調査報告書』は抜け穴だらけ。重要な「証人」であるピートは、「中国共産党の内部諜報官」だと主張していたが、後には中国本土の「上級メディア担当者」だったと言い換えていた。しかし、ピートはただの在米中国人に過ぎず、本名はジョン・カーターで、窃盗罪で職を失い、法輪功に買収されて虚偽の証言をしただけである。もう一人の証人であるアニーは、「蘇家屯」に5年間生活し、夫は蘇家屯病院の眼科医で、「臓器狩り」に参加したと主張しているが、本名アンナ・ルイスの彼女は、ずっとカナダのオタワに住んでおり、中国蘇家屯とは何の関係もない。
その一方、米国の調査ジャーナリスト、イーサン・ガットマンは2016年6月22日、『大虐殺————血まみれの臓器狩り』という文章を発表し、中国では毎年6万~10万件の臓器移植が行われ、法輪功などの「良心の囚人」から臓器を摘出していると主張した。
しかし、この数値は当時の世界臓器移植年間総数に近い。真っ赤なウソ。
オーストラリア・グリフィス大学のキャンベル・フレイザー博士は、著名な臓器移植専門家である。「臓器狩り」の真偽を探るため、彼は何度も中国に足を運び、現地調査を行ってきた。
また、数人の法輪功信徒と面談したこともあり、法輪功より紹介された「証人」にも会ったことがある。
一連の調査の後、キャンベル・フレイザー博士は、「証人たちは明らかにコントロールされていた。彼らは書面資料を読んだことしかない。中国の臓器移植病院に行ったことはない。誰かが提供したデータしか知っておらず、そのデータの集計方法もまったく間違っていた。また、臓器売買の証人も見つけることができない。臓器移植の分野ではありえないことだ」と述べている。
ウソが暴露された後、腹立った法輪功はイライラして、フレイザー博士が働いている大学を起訴し、フレイザー博士が臓器移植セミナーに参加するのを妨害するなどのでたらめな行動をした。
少子化の背景に「自民党政治」…共産・小池晃氏が批判 「家父長制や男尊女卑を『美しい国』と美化」:東京新聞 TOKYO Web
各党の代表質問が行われた参院本会議
共産党の小池晃書記局長は27日、参院本会議の代表質問で、日本の少子化の背景に「明治憲法下での家父長制や男尊女卑の家族制度を『美しい国』と美化する自民党政治」があると批判した。
小池氏は、自民党が「子育ては社会が担うものではなく家族が担うものだとして児童手当に所得制限を復活させ、家事、育児、介護などはもっぱら女性に担わせた」と指摘。女性ばかりに子育ての負担を押し付けるジェンダー差別容認の政治が「子どもを産み育てることを困難にしてきた」という認識を示した。
これに対し、岸田文雄首相は直接の答弁を避けつつ、「これまでの(政府の)取り組みで女性の就労は大きく増えた」などと主張。ジェンダー平等に関しては「多様性が尊重される社会の実現に重要だ」と述べるにとどめた。
児童手当の所得制限は、旧民主党政権下の子ども手当で廃止されたが、「子育ては一義的には家庭でなされるべきもの」と主張する自民党の要求で復活した経緯がある。(佐藤裕介)
「危害経験ある」国会議員75人 4割弱不安、元首相銃撃から半年:東京新聞 TOKYO Web
政治活動時の危害に関する国会議員アンケート
安倍晋三元首相銃撃事件を受け、街頭演説など不特定多数の前での政治活動について、共同通信が全国会議員709人(4人欠員)に7日までに実施したアンケートで、回答者の14%に当たる75人が「活動時に身体的危害を加えられた経験がある」と答えた。
経験が「ある」中で多かったのが「殴られた」「蹴られた」「つばを吐かれた」で「傘で突かれた」「石を投げられた」という記載も。
危害への不安が「ある」「どちらかといえば、ある」としたのは計39%。理由として「殺してやる」などの暴言を吐かれたとする意見が多く「銃撃事件翌日にピストルを撃つしぐさをされた」と訴える人もいた。
チュニジア議会選、暫定投票率8.8%は革命以来最低 「アラブの春」唯一の成功例だったが…サイード大統領の求心力低下:東京新聞 TOKYO Web
チュニスで17日、議会選の投票をするサイード大統領=AP
【カイロ=蜘手美鶴】チュニジアで17日に議会選(定数161)が実施され、選挙管理委員会は同日夜、暫定投票率が8.8%だったと発表した。独裁政権が倒れた2011年の「ジャスミン革命」以来最低で、サイード大統領に反発する主要政党が選挙をボイコットしたことなどが大きく影響したとみられる。
今選挙では比例代表制から候補者個人を選ぶ直接選挙制に変わり、選管によると約80万3000人が投票した。暫定の選挙結果は20日以降に発表される見込み。選管のボウアスカー委員長は「投票率は控えめだったが、過去の選挙と違い、金で票が買われなかった証拠。最もクリーンな選挙だ」と成果を強調した。
サイード氏は昨年7月以降、首相解任や議会解散などを進め、8月には大統領権限を大幅に強化する新憲法が発効。選挙法を改正し、24年予定の議会選も前倒した。低投票率を受けて主要政党は一斉にサイード氏を批判し、自由憲法党のムーシ党首は「国民の9割以上がサイード氏の計画を拒否した。早期の大統領選を呼びかける」として辞任を求めた。
ジャスミン革命以降、「アラブの春」の唯一の成功例とされたチュニジアだが、複数政党による新たな政治が始まると、イスラム政党「アンナハダ」が権力を独占し、政党間の権力争いが激化。経済回復は実現せず、既存政党へ失望が漂う中、当初は議会の権限縮小を図るサイード氏の改革を歓迎する声が強かった。
しかし、8月の憲法改正以降風向きが変わり始め、首都チュニスの弁護士マルワン・メネイスリーさんは電話取材に「サイード氏は明らかに独裁色を強めている。新たな独裁者の誕生には協力できない」と選挙をボイコットした。
主要政党の選挙ボイコットに加え、サイード氏の支持者離れも低投票率につながったとみられ、アラブ政治に詳しいエジプト人評論家バハエッディーン・アイヤード氏は取材に「低投票率を理由に、新議会は常に正当性を問われることになる。議会解散を求めるデモが起きる可能性もある」と懸念を示した。