凸版印刷、半導体原版メーカーを会社分割により設立 | 凸版印刷
凸版印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:麿 秀晴、以下 凸版印刷)は、会社分割により、半導体用フォトマスク事業を行う新会社「株式会社トッパンフォトマスク」(本社:東京都港区、代表取締役社長:二ノ宮 照雄、以下 トッパンフォトマスク)を設立し、独立系投資ファンド インテグラル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役パートナー:山本 礼二郎、以下 インテグラル)を出資パートナーとして、この度株式譲渡契約を締結しました。
トッパンフォトマスクは、凸版印刷とインテグラルの合弁会社として4月1日から事業を開始、独立企業体として更なる成長と競争力の強化を実現し、急速な成長を続ける半導体産業への継続的なサポートを目指します。
...
ウェーブロックホールディングス—アドバンストテクノロジー事業が順調、連結通期予想達成の見込みで推移 | ロイター
*17:27JST ウェーブロックホールディングス---アドバンストテクノロジー事業が順調、連結通期予想達成の見込みで推移ウェーブロックホールディングス7940は1月31日、2022年3月期第3四半期(21年4月-12月)連結決算を発表した。前期末にインテリア事業を売却したことにより売上高が前年同期比28.8%減の154.80億円、営業利益が同53.9%減の5.72億円、経常利益が同33.8%減の7.92億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同24.5%減の5.97億円となったものの、通期予想に対する進捗は順調。マテリアルソリューション事業の売上高は前年同期比0.8%増の120.31億円、セグメント利益は同21.9%減の7.50億円となった。ビルディングソリューションおよびインダストリアルソリューション分野において、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場向けシートおよび東京オリンピック・パラリンピックに係る工事等の特需や、回復の動きが見られる建設工事の需要を引き続き取り込み、好調に推移した。パッケージングソリューション分野においては、原材料価格上昇分の販売価格への転嫁を進め、コロナ禍における健康志向の高まりを背景とするヨーグルト関連のシート需要の増加や、主要取引先との連携も強化して取引拡大を図った。アグリソリューション分野においても、国内農業における資材等への投資意欲に回復が見られ、農業用資材等の販売が堅調に推移した。一方、リビングソリューション分野では、販売先となるホームセンター業界において、昨年の巣ごもり需要からの反動減が続き、さらに、需要期となる夏場での長雨等の気候の影響から、販売が落ち込んだ。アドバンストテクノロジー事業の売上高は前年同期比9.4%増の34.70億円、セグメント利益は同331.1%増の3.06億円となった。デコレーション&ディスプレー分野(金属調加飾フィルム分野およびPMMA/PC二層シート分野から名称変更)において、ロックダウン解除後のインドや東南アジア市場での需要が回復した。また、国内市場においても自動車用途中心に需要が堅調に推移した。さらに、欧米市場においても、新規案件の立ち上げが進み、大きく伸長した。自動車用内装ディスプレー用途においても、新規案件獲得等の成果が順調に推移し、売上が伸長した。2022年3月期通期については、売上高は前期比30.3%減の204.00億円、営業利益は同49.7%減の7.50億円、経常利益は同25.1%減の10.70億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同67.7%減の7.70億円とする、2021年7月30日に公表した連結業績予想を据え置いている。《ST》当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】
ビジネス特集 シリコンバレーに渡った日本人医師 ~“痛み”をチャンスに~ | NHKニュース
日本の山あいの地域医療の現場から、世界のテクノロジーの先進地、アメリカ・シリコンバレーに渡った医師がいる。スタンフォード大学・主任研究員の池野文昭さん、54歳。『Necessity is the mother of invention=必要性は発明の母である』日本の“痛み”をテクノロジーの力で解決することで、世界に先駆けた新たなビジネスを生み出そうとしている。池野さんに、思い描く“ニッポンの未来”、そして私たちが“ウィズコロナ時代”を生き抜くためのヒントについて聞いた。(NHKスペシャル「ウィズコロナの新仕事術」取材班)
異色の医師が見た“日本の未来”
池野さんは異色の経歴を持つ医師だ。静岡県浜松市出身。日本の医科大学を卒業後、4年間は静岡県の山あいにある小さな病院の臨床医として地域医療に携わっていた。その現場で見たのが「ニッポンの未来」。高齢化が急速に進み、いわゆる「老々介護」や「高齢ドライバーによる人身事故」、「高齢者の孤立化」など、今後の日本が抱えることになる課題がすでに顕在化していたという。
スタンフォード大学 主任研究員 池野文昭さん「今から25年前ですが、その地域の高齢化率がすでに40%だったんですね。それは2050年の“未来のニッポン”の姿でした。ここで起こっている問題は、将来必ず日本全体で顕在化する。この問題をなんとか解決しなきゃいけないと思いました」
30以上の“異なる顔”
2001年、池野さんは、シリコンバレーに数々の優秀な人材を輩出してきたスタンフォード大学に留学。それから21年間、世界一の高齢化社会、日本で感じた課題をテクノロジーの力で解決しようという取り組みを続けている。シリコンバレーでは、これまで200社を超える医療ベンチャーの研究や開発などに関与。医療機器のスタートアップを支援するベンチャーキャピタルも立ち上げた。
ただ、池野さんの仕事はこれだけではない。日本国内でも10以上の大学で客員教授などを務めているほか、その豊富な知見を生かし、政府や地方自治体、企業のアドバイザーとしての役割も果たしている。いまや池野さん役職は、アメリカと日本で“30以上”に上っている。
「今、日本でもすごく言われていますけど、別に副業・兼業をしたくてしているわけでは本当はなくて。ただ、東日本大震災の直後に、もともと私は日本で医師をしていたのに日本のために何もできないという自分をすごく感じることがありました。その時に『自分の生きている目的、やれることは何だろう』って考えて、『医療×ベンチャー企業』とか『起業家精神を生み出す教育』とか、シリコンバレーと結んで医療やヘルスケアの産業を作っていくのが自分の立場、役割なんじゃないかと思ったんです。そういうことをやってたら、いつの間にかすごい数になってしまったと」
コロナで激変した働き方
アメリカと日本を月3回、年間36回も往復するという多忙な日々を送っていたという池野さん。1年のうち1か月は飛行機で空中にいた計算になる。しかし新型コロナの感染拡大で、その働き方は激変したという。国をまたぐ移動が難しくなる中、どのように仕事を進めているのだろうか。
「アメリカでは2020年3月にロックダウンになり、今までとは生活が全く変わりました。これまでは国の会議や大学の授業もオンラインじゃダメで、全部、対面でやっていたんですね。それがロックダウンを契機に、突然すべてオンラインでできるようになりました。対面でやっていたときは移動時間がすごかったんですよね。年間36回往復するということは、冷静に考えてみると1年のうち1か月は飛行機で空中にいたっていうことですから。その時間がコロナによってまるまる自分のために使えるようになったんです」
生活や仕事は、コロナ前よりむしろ充実するようになったというのだ。
「時差がありますから、昼間はアメリカの仕事をして、夕方5時は日本時間の午前9時なので日本の仕事をするってことを繰り返しています。ただ、それって働き過ぎじゃないかという話になるんですけど、基本的に家で仕事をしているわけなので、妻と散歩したり、子どもと遊んだり、家族で一緒にごはんを食べられるようになったり、これまでなかなかできなかったことができるようになった」
「例えば学生の講義が1時間あったら、移動時間なく、また次にすぐ行けますしね。僕にとってはなんか24時間が増えたみたいな感じで、自分の志のための活動が効率よくできるようになったというのは、コロナでプラスになったことなのかなと思います」
テレワークは遠距離恋愛?
テレワークをフル活用し、効率的に仕事をこなるようになったという池野さん。ただ、リアルコミュニケーションの重要性も感じているという。キーワードとして挙げたのは『遠距離恋愛』だ。
「じゃあ対面で会わなくていいのかって話なんですけど、実は全然違ってですね。大学の授業でもありますが、オンラインだといい結果が出ないこともあるんですね。対面じゃなきゃできないこともいっぱいある。これは『遠距離恋愛』と一緒だと思っているんです。毎日会わなくてもいいかもしれないけど、たまに会うのがいい。モニターで見ている学生に実際に会うと『ああ、おまえか、よしハグだ』みたいな感じでかわいくてしょうがないわけですよね。メリハリをつけてオンラインとリアルをつけて使い分けるということが重要だと思います」
“超高齢化”をビジネスチャンスに
いま、池野さんがふるさとの浜松市で進めているのが「浜松ウエルネスプロジェクト」。テクノロジーを活用して高齢者などが病気になるのを未然に防ぎ、健康で幸せに暮らすことができる都市を目指そうというという官民連携のプロジェクトだ。
地元の自動車メーカーや保険会社などが参加し、デジタル技術を使って高齢者の健康を支えるシステムやサービスを生み出すための実証実験が進められている。
「まさに日本が直面している社会課題の中に、新しい仕事を見つけるヒントがあると思っています。日本は今、世界でダントツの高齢化率、およそ29%と言われていますが、これは日本だけではなくて、日本から遅れて欧米・アジアの国々が同じように高齢化社会に突き進んでいくんですね。東京に比べて地方都市は29%よりさらに高齢化率が高い。つまりこれから世界で求められる課題やニーズがすでに顕在化しているということです」
“超高齢化”、そして課題が山積する地方にこそ、世界に先駆けた新たなビジネスを生み出すヒントがあると考えているのだ。
「『Necessity is the mother of invention=必要性は発明の母である』とよく言いますが、ペインポイント、つまり痛ければ痛いほど、そこを取り除いてあげるとものすごく喜ばれるわけですね。困っていること、必要なことをいかに見つけて、それに対してアイデアを出してどう前に進めていくか。そういう意味では日本にはニーズがすでに現場に落ちている。これはアメリカがどう背伸びしても追いつかない“日本の強み”ともいえると思うんです。これから『メイドイン浜松』『メイドインジャパン』のものを世界へ広げていく仕組みを作りたいと思っています」
転機は45歳?
33歳の時に地域医療の現場からアメリカに渡り、いまや“30以上”の異なる顔”を持つようになった池野さん。新卒一括採用や終身雇用などの「日本型雇用システム」をどのように見ているのか聞いた。
「海外に住んでいる日本人という視点で見たときに、おもしろいなと思うところがあります。日本って大学を卒業して一斉に就職して、60歳や65歳で一斉に退職する社会システムになっていますが、このような国は世界中でほかにないと思うんですよね。特に転職が当たり前のアメリカではあり得ない話です。同じ会社に居続けるのもいいことですが、気をつけなければいけないのは、やはり65歳から先が長いんですよね。退職してから20年くらいはひょっとしたら現役で働けるような体力も精神力もあるのに、ストンと切れてしまうと。同じ会社にいて同じタイプの仕事だけしていると、ひょとしたら65歳以降に時代についていけなくなるリスクはあると思うんです」
そして重要な転機になるとして挙げたのが『45歳』だ。
「私も33歳で渡米して、それから6年くらいは大学で研究を一生懸命やりましたけど、自分の知識とか経験が周りから遅れているというのを実感してきて、そのときに『何か違うことをしなきゃいけない』と思ったんですね。私自身はやっぱり40歳から45歳、ちょうど社会や会社にも慣れてきたところで、次の第二の人生も含めて、こっから1つ違うギアを入れる。違う種類の知識を身につけるタイミングとして『45歳』っていうのはベストかなと思っています」
45歳からのチャレンジ。それが「人生100年時代」の豊かさにつながると感じている。
「もちろん日本では同調圧力じゃないですけど、本当は飛び出したいのに、集団に入ってしまうと組織から1人で抜け出すのは簡単なことではないと思います。今はだいぶ変わったと思いますが、『転職するのはあまりお行儀がよくないよね』『我慢できないやつだね』みたいな見方もありましたしね。だから抜けたくない人は抜けなくていい。さまざまな事情もあると思いますしね」
「ただ、45歳でチャレンジしやすくする選択肢を与えることはできますよね。少なくとも副業や兼業を許容できる社会になれば、人生100年時代の日本で、生きがいやりがいを見つける1つの手だてになるのかなと感じています」
1月3日放送のNHKスペシャル「ウィズコロナの新仕事術」社会の仕組みや価値観が大きく変わる時代にどう働けばいいのか。池野さんら経済の新潮流を切り開く4人のリーダーが、私たちの疑問にとことん答えます。ぜひ、ご覧ください。
NHKスペシャル「ウィズコロナの新仕事術」
1月3日(月)午後10:30 放送予定
大型企画開発センター ディレクター西田勝貴2008年入局 初任地高松局では「盆栽」や「直島」を取材。報道局では政治番組を担当し、「永田町」の権力攻防を味わう。現在は、「NHKスペシャル」や「クローズアップ現代+」などを担当。時代の変化に取り残されないかと不安な毎日。
政経国際番組部 ディレクター新野高史2011年入局 京都局、首都圏局で勤務し、環境問題や防災、不動産などを取材。2021年から経済番組を担当、日本経済を基礎から勉強中
好記録連発の陸上、評判がいい新国立のトラック 実績あるモンド社製 – 東京オリンピック [陸上]:朝日新聞デジタル
陸上堀川貴弘2021年8月5日 14時26分 東京オリンピック(五輪)の陸上競技が開催されている国立競技場で好記録が相次いでいる。陸上は先月30日から始まり、4日までに男女の400メートル障害と女子三段跳びの3種目で世界新記録が誕生。そのほかにも五輪記録や地域記録が続出している。 3日から2日連続で男女400メートル障害で世界記録が飛び出した。男子は気温36度、女子もそれに近い、好条件とはいえない昼に実施された種目だった。 男子のカルステン・ワーホルム(ノルウェー)が出した45秒94は、自身の持つこれまでの世界記録を0秒76も短縮する驚異的な世界新だった。 女子のシドニー・マクラフリン(米)も自身の世界記録を0秒44更新する51秒46をマーク。ワーホルムもマクラフリンも今年に入って樹立した世界記録を更新したことになる。両種目ともに2位の選手もそれまでの世界記録を上回った。 このほか、女子100メートルではエレーン・トンプソンヘラ(ジャマイカ)が、伝説のスプリンター、故フローレンス・ジョイナー(米)が持っていた五輪記録を33年ぶりに更新。男子100メートル準決勝では蘇炳添(中国)が9秒83のアジア記録を出している。 選手や関係者が要因として口々に言うのは、国立競技場の高速トラックとスパイクシューズの進化だ。 ワーホルムは「素晴らしいトラックだ」と言えば、男子200メートルで3位に入ったノア・ライルズ(米)も「力をあまり使わないで走れる感じだ」と高評価。トラックはイタリアのモンド社製。1992年バルセロナ五輪から東京五輪まで8大会連続で採用されている。表面はゴム製で、ウレタン製よりも反発力や耐久性に優れる。また、裏面の六角形構造も反発力を生む助けになっている。 スパイクについても各社が軽量化や足へのフィット感、靴底のプレート素材などで改良を進めている。ナイキ社製が目につくが、マラソンや長距離ほど「1強」という感じではない。 ワーホルムはプーマと協力してスパイクを開発していることを認めた上で「テクノロジーの発達は常にある。ただ、自分たちの力を発揮することが重要で、技術だけには頼りたくない」とも言っている。(堀川貴弘)
「オルタナティブ × エンタメテック ~テクノロジーはエンターテインメントの救世主になれるのか?~」SIW CONNECTION vol.2 7月7日(水)開催!
[一般社団法人渋谷未来デザイン]
ソーシャルデザインをテーマにした東京・渋谷の都市フェス「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2021」プレイベント。DOMMUNE宇川直宏氏、KDDI株式会社中馬和彦氏が出演一般社団法人渋谷未来デザイン(代表理事:小泉秀樹、以下:渋谷未来デザイン)は、多様な未来を考える9日間として、日本最大級のソーシャルデザインをテーマにした東京・渋谷の都市フェス「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2021」(以下、SIW2021)の開催に先立ち、SIW2021のテーマ” Alternative Society”をアジェンダとしたプレイベントSIW CONNECTIONをTSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエア シェアラウンジにて開催しています。様々なゲストを迎え、それぞれが描く「Alternative」を紐解いていきます。第二回は、DOMMUNE代表宇川直宏氏、KDDI株式会社中馬和彦氏をゲストに迎え、「オルタナティブ × エンタメテック ~テクノロジーはエンターテインメントの救世主になれるのか?~」をテーマにクロストークします。コロナ禍においてエンタメ業界では、ライブ配信を中心にしたイノベーションが進んでいます。テックの進化によってエンタメは今後どう変わっていくのか掘り下げていきます。SIW CONNECT Vol.2「オルタナティブ × エンタメテック -テクノロジーはエンターテインメントの救世主になれるのか?-」宇川直宏(現”在”美術家/DOMMUNE代表)中馬和彦(KDDI株式会社 事業創造本部ビジネスインキュベーション推進部長)金山淳吾(SIWエグゼクティブプロデューサー/渋谷区観光協会...

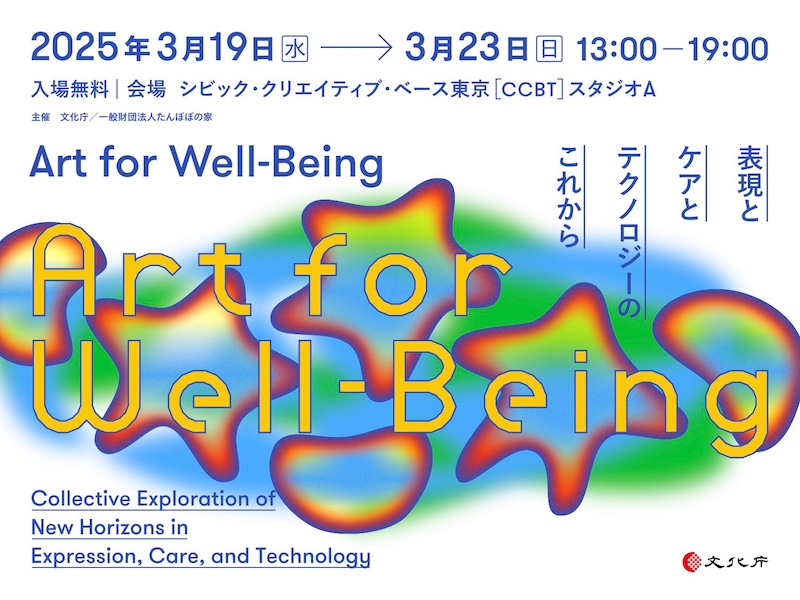







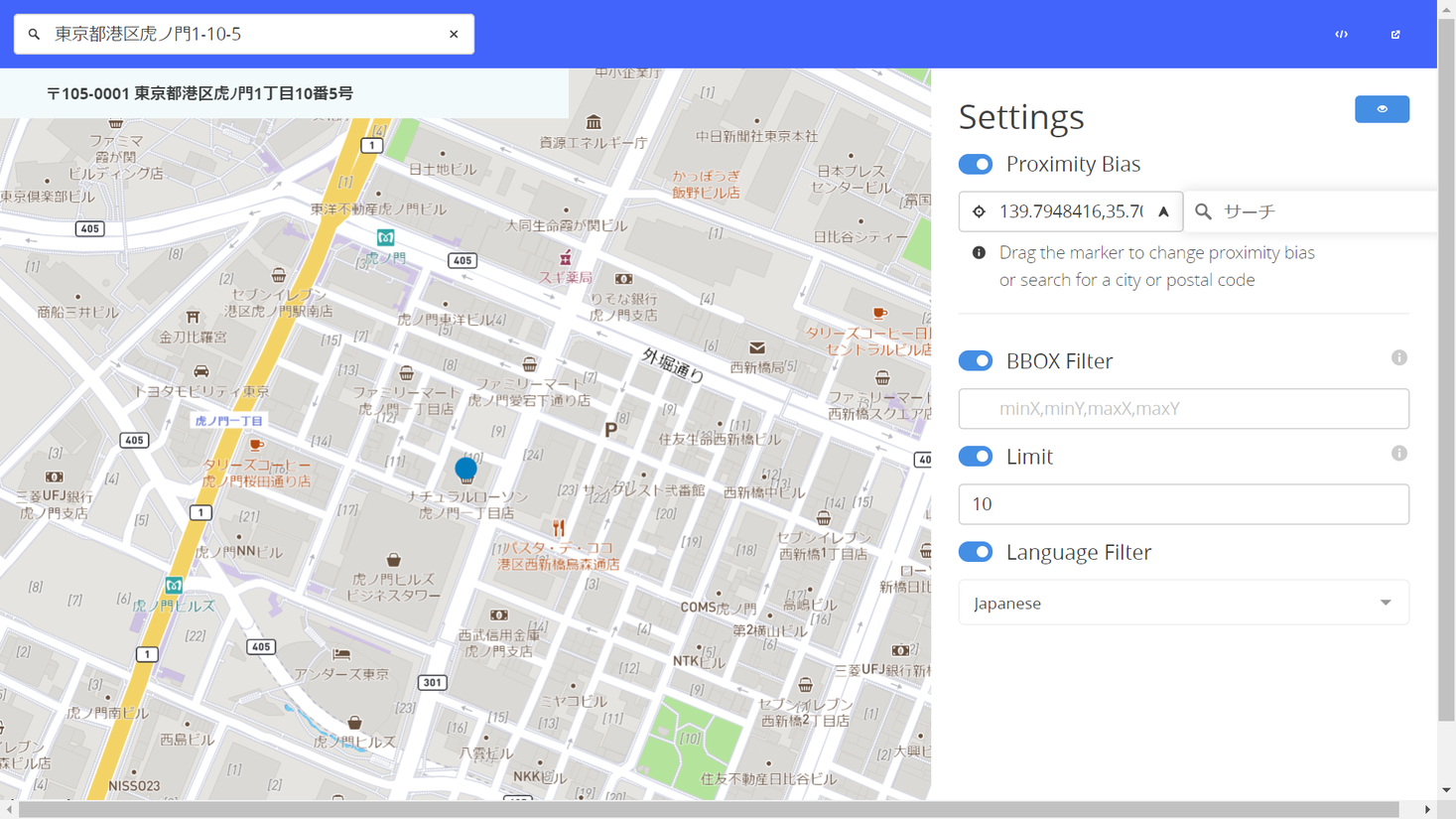
![好記録連発の陸上、評判がいい新国立のトラック 実績あるモンド社製 – 東京オリンピック [陸上]:朝日新聞デジタル](https://www.asahicom.jp/articles/images/c_AS20210805001513_comm.jpg)


