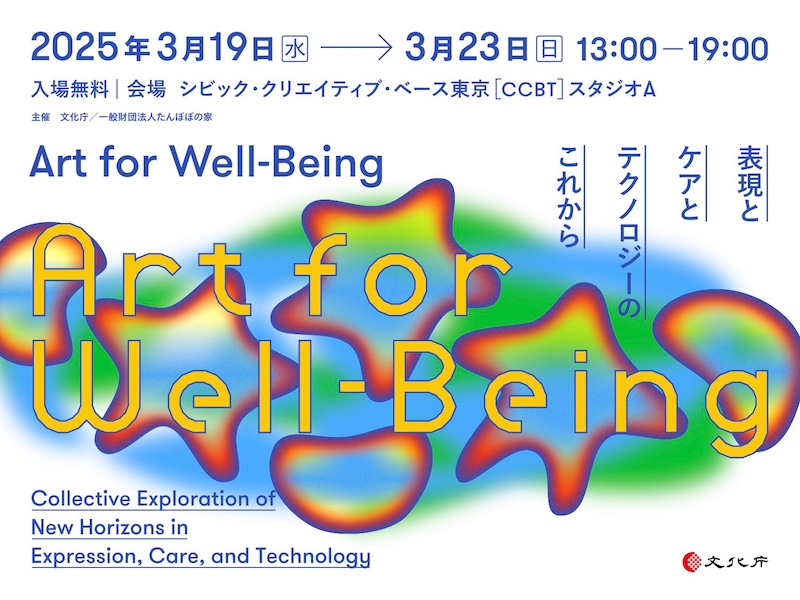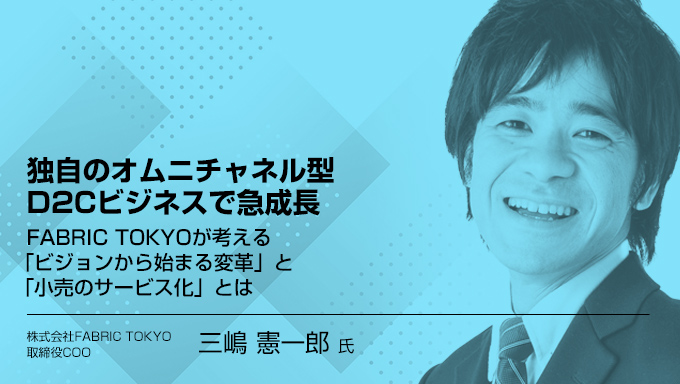「役に立つのは、10年先でもいい」。量子コンピュータベンチャーに三菱電機が出資する理由 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)
三菱電機グループとスタートアップを繋ぐ架け橋として2022年1月に設立された「MEイノベーションファンド」。有望なスタートアップに投資し、共創を通じて、次世代を見据えたイノベーションの社会への実装を目指している。22年5月に第1号案件として量子コンピュータ関連ベンチャーのQunaSys(キュナシス)への出資を発表したが、決定までは立ち上げから2カ月だったという。このスピードで出資を決定づけた理由は何か。そしてともに見据える未来とは。新たに始まった共創に携わる4名に話を聞いた。
「不安」と「戸惑い」から始まった共創出合いのきっかけと決断の動機
出資検討に向けて、意見交換の時間をいただけないだろうか——。QunaSysのCEO、楊天任のもとへ、三菱電機MEイノベーションファンドからのオファーが届いたのは、2022年2月のことだった。シリーズBラウンドの資金調達をしているタイミングだったものの、量子コンピュータ関連のベンチャーであるQunaSysが当時手がけていたのは、材料のシミュレーションという分野。三菱電機とダイレクトに繋がる分野ではないことから、戸惑いを感じた、と楊は語る。「これまでお付き合いがあったのは民間のベンチャーキャピタルや、事業分野につながりのある会社でしたから、お声がけいただいた理由が分かりませんでした」(楊)QunaSys CEO 楊 天任量子化学計算系のアルゴリズム、ソフトウェア開発に強みを持つQunaSysは、三菱電機の事業とは直接的な接点がない。そこをなんとかして繋げることはできないか、という不確実性へのチャレンジだった、とその理由を語るのは、MEイノベーションファンドの投資担当、峯藤健司だ。“チャレンジャーであり続ける”ことは、MEイノベーションファンドが掲げる理念の一つでもある。「不確実性の高い世の中だからこそ、CVCファンドの強みをいかして挑戦する姿勢をこの一号案件で社内外に示したい、という想いがありました」(峯藤)三菱電機 ビジネスイノベーション本部コーポレートベンチャリング推進グループ 峯藤健司2022年1月のMEイノベーションファンドの設立から、QunaSysへの出資決定までに要した時間はなんと2カ月足らず。あくまでスタートアップファーストという立場をとり、資金調達面でも意思決定の場面でも、スタートアップに寄り添う姿勢を貫く。自身も元研究者という経歴をもつ峯藤の柔軟な考え方、スタートアップに寄り添う姿勢、さらに先端技術総合研究所で行われている量子コンピュータの研究にも惹かれるものがあったと楊はいう。加えて、三菱電機がもつ社会との強いつながりも、大きな理由になった。「量子コンピュータはまだ実用化には至っていない、研究段階にある分野です。技術の研究はもちろん大切ですが、QunaSysとしてはそれに留まらず、その技術をどう社会に役立てていくか、というところまで考えていきたい。三菱電機さんは圧倒的に社会と繋がりをもっているので、新しい領域の開拓や技術を作りつつ、社会への実装まで一緒に考えていけます。QunaSysが挑戦したい領域に興味を持ってくれているので、自社独自でやるよりも、社会に繋がりやすい。そういう研究ができるのは、我々にとって、とても大きいです」(楊)共同研究でつまずかない。本当の共創を実現させるために不可欠な施策とは
MEイノベーションファンドの設立以前からスタートアップ支援に携わってきた峯藤が、今回の出資にあたり最も頭を悩ませたのは、社内のカウンターパートに誰を立てるかだったという。共同研究を円滑に進めるためには、技術理解や相性は重要な要素だ。そこで白羽の矢を立てたのが、研究者として先端技術総合研究所で量子コンピュータの利活用の技術開発などを手がける牧野兼三だった。以前からQunaSysに注目していたと語る牧野だが、異なる2社の強みをどうあわせた研究をするべきか、想像できなかったと語る。「研究のテーマ選びは、研究でどんなことをするか以上に大事なことなのです。いきなり共同研究となると、なにも準備せずにテーマを作ることになるので、お互いにやりたいことや言いたいことを言うだけになったり、気がついたら違う方向を向いている状態にもなりかねません」(牧野)三菱電機 開発本部 先端技術総合研究所 牧野兼三どれだけ一生懸命考えてステップを踏むか、準備や手順を考えたか。共同研究ならなおさら、それらは後行程になればなるほど、その研究がスムーズに進むかどうかに関わってくるという。そこで今回取り入れたのが、“リサーチデザイン”という期間だ。峯藤はこのリサーチデザインを「これから同じ船に乗って航海をするために、どの方向に進むのか、誰がどのような考え、意見を持っているのか、あらかじめ知るための時間」と表現するが、数ヶ月かけて、既存研究の紹介や、現在の量子の問題点を議論し、取り組みの方向性をとことん話し合った。QunaSysでリサーチマネージャーを務める菅野恵太は、リサーチデザインを次のように振り返る。「研究の中身はもちろんですが、人と人が共に作業するシーンでは、考え方や問題の解き方などの感覚が全然違うとやはり難しい。それを確かめられたという点でも、非常に有意義な時間でした。牧野さん達は、量子コンピュータに関する論文をしっかり読み込み、技術的なことも深く理解して、リサーチデザインの席に着いてくれました。バックグラウンドも含め、一緒にやっていけるという安心感を得られたことは、これからの共同研究においてとても大きいと思います」(菅野)QunaSys リサーチサイエンティスト 菅野恵太こういったある意味“腹を割って話せる環境作り”は特に重視していると峯藤はいう。短期的な付き合いなら、成果だけに集中することができる。しかし、中長期で関わる共同研究ではゴールまでの道のりは長く、人同士の相性や好みなどにも折り合いを付けながら共に進む必要がある。それが決して押しつけになることなく、価値観や文化を共有しあい、Give&Give で向き合っていくことこそ、MEイノベーションファンドの目指すところでもあるのだ。リサーチデザインというプロセスを通して、今の技術を正しく理解してもらえたのもよかった、と楊も続ける。「いくら量子コンピュータがすごいとはいえ、2〜3年後に何かが劇的に変わるわけではありません。そこの理解はなかなか得にくいことが多いのです。可能性ばかりを語るのではなく、不可能なことやリスクにおいても、自分たちが感じていることをそのまま素直に伝えられる関係はとてもありがたいし、そういったコミュニケーションは、これからも大切にしていきたいですね」(楊)あらたなテクノロジーと社会を繋ぐために。すぐ先の未来ではない、もっと先の世界を見据えて
リサーチデザインを9月に終え、その成果をもとにした共同研究はこれからスタートする。だが、そもそも量子コンピュータは今のところまだ実用化には至っていない分野。特殊な計算の領域で使えるデバイスになりそうだということがわかりつつある段階でしかない。それでも、実験では興味深い結果が多く集まりつつある、と菅野はいう。「量子コンピュータが面白いものであることは、もう間違いない。研究が進めば、人類が今まで使えなかったものが使える時代が必ずやってきます。でもそれが、どのくらい先になるかは、今はまだ見えません。技術の進化は早いので、すぐに役立つ技術を短期間で開発しても、それはすぐに廃れてしまいます。時間をかけて、本当に役に立つ、長く使えるものを開発していきたい。だから、それを理解し、同じ思いを持ってくださっている牧野さんはじめ三菱電機さんとの共同研究は、とても心強いですね」(菅野)しかしながら、MEイノベーションファンドがCVCである以上、気になるのはリターンの部分だ。まだどんな役に立つのか、それがいつになるのかもわからない量子コンピュータの分野で、どんなシナジーを生み出していくのか。三菱電機の二人はこう説明する。「今は、量子コンピュータがどう役立つのかを探していくことを、第一のミッションに掲げています。アルゴリズムのコアの部分をQunaSysさんに相談しながら、事業への応用の可能性も探っていくのが、一つの大きな目標ですね。ただそれだけでなく、そこに至る過程において学術的な成果を出すことも、重要視しています。どんな学会や論文に出したいかというレベル感もとても近いと感じているので、そういうところでもぜひ一緒にやっていきたいと思っています」(牧野)「相互理解が深まるとか、ナレッジが蓄積されるということも、短期的に得られる成果の一つだと思っています。副次的なものではありますが、それを積み重ねることが、中長期の成果に繋がっていくはずです。共同研究を通じて新しいプロダクトや事業を創っていくことができれば、それこそ素晴らしい成果です。日本の製造業の強みを活かして、日本を元気にしていきたいですね」(峯藤)三菱電機との共創への思いについて、楊はこう締めくくった。「これからのスタートアップは、純粋にテクノロジーを磨くだけではどうにもならないと考えています。量子は革新的な分野ですが、企業として、基礎研究を通して積み重ねた膨大な成果をどう社会に還元していくかまで、しっかりと考える必要があります。とはいえ、社会へつながるものを1から作りあげていくのはスタートアップには荷が重すぎます。既にそのつながりを持つ三菱電機と一緒に考えながら取り組むことで、スムーズな研究とよりよい成果へと繋がることを、今は期待しています。量子コンピュータはまだ研究段階で、社会に役立つ研究か否か、はじめから狙って研究できるものではありません。だからこそ、試行錯誤をくりかえし、こんなことができるかもしれないという妄想を定期的に繰り返していくことは、とても重要だと考えています。その妄想を信じて作り上げていくことが、新しい技術の実用に繋がっていくのではないでしょうか」(楊)QunaSysは、量子物理学を利用して既存のテクノロジーで成しえなかったことを実現するために、大学の研究室から派生したスタートアップだ。在籍するスタッフはそのほとんどが研究者であり、企業文化もよりアカデミアに近い。その文化を深く理解し、共に歩める土壌が、研究所を有し、社内に研究職を多く抱える三菱電機にはある。その2社がタッグを組むことで、どんなシナジーが生まれるのか。共創は今まさに、はじまったばかりだ。三菱電機https://www.mitsubishielectric.co.jp/QunaSyshttps://qunasys.com/峯藤健司◎三菱電機 ビジネスイノベーション本部。研究職として入社後、光通信技術の研究開発に従事。研究開発戦略策定や資源配分を担当した後、オープンイノベーションを起点とした新規事業開発の推進を担い、スタートアップのハンズオン支援を数多く経験。MEイノベーションファンドの立ち上げを主導。牧野兼三◎三菱電機 先端技術総合研究所 センサ情報処理システム技術部 主席研究員、博士(工学)。量子情報処理、センサ計測技術の研究開発に従事。自動車、交通、電力、ビル事業のセンサ開発を担当した後、量子コンピュータの情報処理能力に着目し研究テーマを立案、現在は量子コンピュータ活用技術の研究開発を主導。楊 天任◎QunaSys CEO。1994年生まれ。2016年に東京大学工学部機械情報工学科を卒業し、同大学院の情報理工学系研究科知能機械情報学専攻に進学。在学中の2018年2月に株式会社QunaSysを設立。量子コンピュータを社会の役に立たせることを目指し、量子コンピュータの用途を広げるアルゴリズムの研究を行いながら、量子コンピュータを利用するためのソフトウェア開発に取り組んでいる。菅野恵太◎QunaSys Research Scientist。東京大学理学系研究科物理学専攻にて、素粒子論の研究を行い、博士(物理学)を取得。2021年4月に量子情報エンジニアとしてQunaSysに入社、量子アルゴリズムの研究に従事。2022年より現職にてリサーチチームのマネジメントを行う。
テクノロジーと音楽の祭典「イノフェス」、10/22(土)&23(日)のタイムテーブルと トークセッション概要解禁! 福岡ソフトバンクホークス前監督の工藤公康ほか 追加出演者も発表! | J-WAVE NEWS
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、今年で7回目の開催となる日本最大級のデジタル・クリエイティブフェス「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2022」(以下、イノフェス)を、2022年10月21日(金)、22日(土)、23日(日)の3日間、六本木ヒルズで新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、有観客とオンライン配信のハイブリッドで開催いたします。この度、福岡ソフトバンクホークス前監督の工藤公康ほか追加出演者が新たに決定! あわせて、タイムテーブルと各トークセッションのテーマなど、ステージ詳細を解禁いたしました。
タイムテーブルURL https://www.j-wave.co.jp/iwf2022/timetable/
今回で7回目を迎える「イノフェス」のテーマは「The beginning of a new world」。長引くコロナ禍や国内外の混乱、そんな先行き不透明な時代に登場したWeb3という概念。NFTやDAO、Metaverseといった、時代を変えてしまうかもしれない新しいテクノロジーやカルチャーが登場してきました。そんな時代の転換点に私たちは今、何をすべきか? 今年のイノフェスではWeb3をテーマに、そのヒントをたっぷりお届けします。
10月22日(土)タイムテーブル詳細
<INNOFES ARENA(六本木ヒルズアリーナ)>
「CHINTAI presents MAP LIVE SHOWCASE」(13:10~)【LIVE】出演:YABI×YABI、堀内洋之、Suhm、東京〇X問題、MC:川田十夢
次世代アーティスト発掘&育成プロジェクト「CHINTAI presents J-WAVE MUSIC ACCELERATOR PROGRAM」のライブステージ。未来の音楽シーンを担うアーティスト4組のパフォーマンスをお楽しみください。
「音楽×NFTから見通す音楽とアーティストの未来」(14:40~)【TALK】出演:亀田誠治、syudou、鈴木貴歩
NFTは音楽シーンに新たなエコシステムを提供するのか? 音楽プロデューサー・亀田誠治が、エンターテックの第一人者・鈴木貴歩、「うっせえわ」の作者でシンガーソングライター・syudouと共に、国内外の事例を交えてWeb3時代の音楽とアーティストの未来を考えます。
「宮本笑里」(15:50~)【LIVE】
クラシックと最新映像テクノロジーが融合した、デジタル・デトックスライブ! ヴァイオリニスト・宮本笑里が、最新映像テクノロジーを駆使して“究極の癒し”をお届けします。
「電音部 INNOFES METAVERSE...
街を天空に向かって伸ばした「垂直都市 THE LINE」 – ナゾロジー
自然環境の保護と居住性を両立させる垂直都市「THE LINE」水平に広がる居住区を直線上にまとめた都市「THE LINE」 / Credit:NEOM(YouTube)_NEOM | What is THE LINE?(2022)垂直都市「THE LINE」は、人類の居住性と自然環境の保護を両立させるために考案されました。都市というものは通常平面方向へ広がっていくものです。しかし動画から分かるように、「THE LINE」は水平に広がっていた建物を重ねて一本の直線上に集め、垂直に断層化しています。THE LINEの規模は、幅200m、長さ170km、高さ海抜500mとのこと。垂直都市に900万人が収容される / Credit:NEOM東京スカイツリーが634m、東京タワーが333m、日本一高いビル「あべのハルカス(60階)」が300mであることを考えると、一般的な超高層ビルの概念をはるかに超えた規模だと分かりますね。ちなみに、アメリカで最も高い建造物である「ワン・ワールド・トレード・センター(104階)」が541mなので、技術的には不可能ではないのかもしれません。また最終的には、900万人の居住者が住む予定なのだとか。神奈川県と同じくらいの人口が収まることを考えると、まさに前代未聞の大規模な未来都市だと言えるでしょう。THE LINEの内部イメージ / Credit:NEOMでは、この新しい都市には、どのような機能が含まれているのでしょうか?垂直都市THE LINEには、生活に必要な施設(公園、学校、家、職場など)が収まります。連なる超高層マンションに、さまざまな施設が収容されているイメージですね。従来の都市のように遠くまで出かける必要がないので、5分以内で日常のニーズを満たせるのだとか。施設が縦に収容されることで、さまざまな施設にすぐにアクセスできる / Credit:NEOMまた居住区間を直線上にまとめることで、車や道路など交通機関の大部分を廃止し、排気ガスを大幅にカットできます。代わりにTHE LINE内の端から端を20分で移動する高速鉄道によって、全ての施設に対して効率的にアプローチできるようです。さらにTHE LINEの外側は鏡で覆われており、外部から見て周囲の景色と一体化するようになっています。居住区を垂直にまとめることで、周囲の自然を保護。外観も一体化させている /...