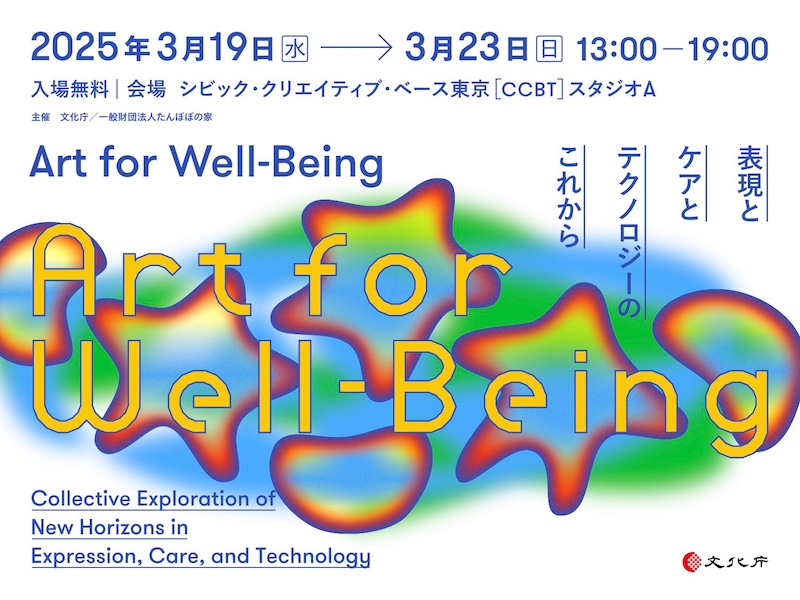ビジネス特集 まさか、駅のアナウンスで ~障害者“痴漢被害”の現実~ | NHKニュース
k10013289921_202110041255_202110041324.mp4
「業務放送。お客様ご案内、3号車。降車駅は○○駅」。駅のホームで流れるこんなアナウンス、聞いたことはありませんか。車いすの利用者や視覚障害者が、電車のドアに挟まれたりしないようにするため、「乗った車両」「降りる駅」、そして「乗り降り完了」の3つの情報を車掌や駅員が共有するためのものです。しかし、この“安全を守るためのアナウンス”が悪用され、障害者への性被害が相次いでいるのです。(経済部記者 真方健太朗)
つきまとい被害 女性の告白
駅のアナウンスがきっかけで、つきまといの被害を受けた女性です。今回初めて、NHKの取材に苦しみ続けてきた胸の内を明かしてくれました。被害にあったのは11年ほど前、自宅付近にスーツ姿の男がいることに気付いたといいます。「なんとなく見覚えがある気がするな…」そんな思いが頭をよぎりましたが、面識は全くありません。しかし、男のつきまといは、その後も1年余り続きました。ある日、男と鉢合わせになった女性。警察に相談すると、夜中に自宅の窓ガラスに大きな石が3つ投げ込まれたといいます。
被害を受けた女性「一瞬、何事かわからなかったんですけど、ガラスが割れて家の中に石が入ってきました。昼間でカーテン開けていたら、けがをしていたかもしれません」
男の供述 “駅のアナウンスであとをつけた”
その後、男は警察に逮捕されましたが、その供述は驚くべきものでした。警察の調べに対して「駅のアナウンスを聞いて女性の降りる駅を特定した。待ち伏せして自宅まであとをつけた」と話したというのです。
「びっくりしたというか、そんなことがあるんだと。どうしようか、また起こるんじゃないか、私以外にも起こるんじゃないか。そればかりを考えていました」
それ以来、女性は電車で1人になることに恐怖を感じるようになりました。特に夜の電車に乗らないようにするため、食事や飲み会に誘われても断るようになったといいます。
「電車に乗るのはいまでも怖いです。いつになっても怖いです。怪しい人が来ても私たちは逃げられません。電車を乗り降りする際にはスロープがないと逃げられませんから。ただでさえ、車いすの人は『邪魔だ』とか『ここは車いすスペースじゃないだろう』って怒られることがあるから、電車の移動中は常に緊張しているんです。起こった被害というのは、忘れることのできない一生の苦しみです」
性被害は30件以上も
長いあいだ、被害のことを誰にも話せなかった女性。しかし、周りの人たちに少しずつ自分の体験を打ち明けると「同じような被害を受けた」という相談が相次いで寄せられるようになりました。女性はことし、みずからも所属している障害者団体「DPI日本会議」と協力して被害の実態を調査しました。すると駅のアナウンスを悪用した痴漢やつきまといなどの被害が、これまでに30件以上もあることがわかったのです。
車いすの利用者「『ここだ!』とスーツ姿の男性が乗ってきた.ぴったり後方にくっついてきて下着の色を聞かれたり、卑わいなことを繰り返された」車いすの利用者「アナウンスはしないでくださいと頼んだのに、それでは乗せられないと断られた。酔った男性が飛び乗ってきて『いた!手伝ってあげようと思って走ってきたよ、○○駅でしょ?』と言いながら繰り返し足をさすられた」視覚障害者「車両のドアのところで外側を向いて立っていたら、『いたいた!手伝ってあげるよ』と言いながら後方に回り、ぴったり迫り、もぞもぞされ、荒い息をされた」
障害者の安全を守るためのアナウンスが悪用されていたという現実。女性は大きなショックを受けました。
「私たちに必要だと思ってアナウンスしていたことが悪用され、先回りしてあとをつけたり、わざわざ乗った車両を見つけ出して卑わいなことしたりしている。この現実を受け止めることができませんでした。被害を受けたからといって、アナウンスが必要な人もいるんじゃないか、自分勝手なことは言ってはいけないのではないかという考えもありました。ただ、もはや『安全のためが安全じゃなくなっている』と思ったんです」
“行動を起こさなければ”
「行動を起こさなければ」女性は被害者一人一人に寄り添い、了解が得られた12人分の被害事例をまとめました。そして障害者団体はことし7月、アナウンスの情報が悪用されているとして、対応を求める要望書を、被害事例とともに国土交通省に提出。国土交通省は、アナウンス以外の情報共有の方法も検討するよう鉄道各社に求めました。
「DPI日本会議」佐藤聡 事務局長「これはもう確実にアナウンスによって引き起こされている問題なので、一刻も早くやめてほしいです。日本の鉄道って安全な乗り物だと思うんですよ。鉄道事業者はすごく安全に気を配ってやってくださっているので、こういう被害が起きているのが分かったのなら改善してもらって、障害者も心配なく乗れるように変えてほしいです」
鉄道各社は対策へ
要望を受けて鉄道各社は対策に乗り出しています。JR東日本の深澤祐二社長は、9月の記者会見で、首都圏の駅で行っているアナウンスを原則、廃止できないか検討する方針を明らかにしました。
アナウンスの代わりに使おうとしているのが、「タブレット端末」です。駅の改札で、障害者から「降りる駅」の情報を事前に聞き、「乗る車両」とともに端末に入力。すると、「降りる駅」の駅員と情報を共有できる仕組みです。
一部の路線で使っているタブレット端末を、今後、ほかの路線にも拡大し、アナウンスの一部を廃止したいとしています。
アナウンスやめたいけど…
ただ、すぐにやめることができないのが「乗り降り完了」のアナウンスです。その理由は首都圏特有の長い列車編成と、乗降客の多さ、そして過密なダイヤにあります。今回取材したJR田端駅は、山手線の中では利用者が少ないほうですが、朝の8時から9時台は通勤ラッシュで混雑し、停車時間は30秒です。
車掌は、このわずかな間に、ホームの様子が映るモニターで安全を確認しながら発車メロディーを流したり、ドアの開閉作業を行ったりしていて、タブレットを使う余裕はないというのです。
さらに、10両編成以上になるとホームの長さは200メートルを超え、ホームの一部が湾曲して見通しが悪いところもあります。NHKがJRや私鉄大手など全国35の鉄道事業者に取材したところ、アナウンスを行っているのは、9月末の時点で「15」の事業者。利用者が多い首都圏や関西圏の事業者を中心にアナウンスが行われていました。
JR東日本サービス品質改革部 佐久間晋副課長「放送を悪用するというのは、許しがたい行為だと思います。ただ、アナウンスを全面的にやめてしまうと、お客様に安心してご利用いただく環境を提供するのが難しくなってしまうんじゃないかと懸念しています。難しいところはありますが、障害のあるお客様に安心してご利用いただける環境を作るのは当社としても重要だと考えていますので、見直すことができないか、検討していきたいと思います」
“見て見ぬふり”しないで
つきまといの被害に遭った女性。今回の調査を行う中で気になることがあったといいます。それは、被害者が勇気を出して助けを求めても、周囲が無関心だったという声が複数あったことです。
車いすの利用者「電車内で男からずっと声をかけられた。やめてくださいと言っているのに周囲の人は誰も助けてくれなかった」車いすの利用者「大きな声を出しても周囲の人は聞こえないふりをしているように感じた」
女性は、周囲の乗客が見て見ぬふりをしなければ、防げる被害もあったのではないかと感じています。
被害にあった女性「声は聞いていたはずなのに、『大丈夫ですか』という声をかけてはもらえなかった事はショックでした。車いすで電車に乗ると、スペースを譲ってくださる方がいますが、多くはただ、すーっと避けていくだけなんです。『ここ、どうぞ』って声をかけてもらえれば、『ありがとうございます』ってその方と対話ができるのに、なんで声に出してくれないのかなと思うことが多いんですね。ただ、『ひと言ことばを交わしたら、きっと社会が変わるんじゃないか』と思うことが多いんです」
あなたのそのひと言で
実は今回の取材、きっかけは東京パラリンピックでした。都内の駅のほとんどにエレベーターが設置され、ホームと電車の隙間を狭くする工事も行われるなど、東京パラリンピックに向けて物理的なバリアフリーが進んでいました。しかし、その感想を障害者団体の方に尋ねたところ、返ってきたのが意外な答えだったのです。「バリアフリーが進んだことはとてもうれしい。ただ、ある理由で電車に乗るのことができなくなっている人もいる」そして駅のアナウンスを悪用した性被害が起きていることを、私に伝えてくれました。「日本ではさまざまな人がコミュニケーションを取って支え合う『心のバリアフリー』が遅れている」専門家はそう指摘しています。困っている人がいたら、ひと言、声をかける。そこから始めてみませんか。
経済部 記者 真方健太朗帯広局、高松局、広島局を経て現所属。国土交通省で鉄道や航空業界の取材を担当。
2023年12月6〜7日、東京ビッグサイトで開催の第3回 東京ビジネスチャンスEXPOにPhotolizeが出展!5社限定で初期導入費用無料+3ヶ月無料の特典付き!業務効率化を一緒に実現しましょう!! | codeless technology 株式会社のプレスリリース
2023年12月6日(水)及び7日(木)東京ビッグサイト東1ホールにて開催される『第3回東京ビジネスチャンスEXPO』に、コードレステクノロジーが出展致します。
出来事は東京サイトビッグ東1ホール となります。
『第3回 東京ビジネスチャンスEXPO』は、Photolizeを多くの企業様に知っていただいて貴重なチャンスと捉えています。中小企業とITベンダーをつなぐ東京商工会議所の「ぴったり」マッチングを大切に、簡単に考えてDXに対応するPhotolizeのご紹介をしていきます。
今年、最後のイベントでPhotolizeの導入を決められた先着5社には、導入初期費用+3ヶ月無料の導入特典を設けさせて頂きます。
この機会にPhotolizeによるシステム導入の使いやすささと簡単さをぜひご体感ください!
当日会場では、Photolizeのブースでは実際のデモンストレーションや、具体的な取り組み内容についての詳細を共有させていただきます。投資家の皆様をはじめ、興味をお持ちの方はぜひお越しください。
『第3回 東京ビジネスチャンスEXPO』にお越しの皆様は、弊社ブースまで是非お立ち寄りください!
▼▼Photolizeは現場担当者がシステム開発を行うようなイメージで、ユーザーから送られた書類をそのまま背景として設置して、その上にデータ入力枠と写真の貼り付け、手描きを可能とすることWEB上で紙のように使用することができます。
▼▼Photolizeのサービス紹介動画(3分)
https://www.youtube.com/watch?v=U1vwCiSG9cA
https://bizchanexpo.tokyo/
■本展示会の特徴
1. 4つの出展分野での販路開拓
本展示会では「フード」「ライフスタイル」「ものづくり」「サービス・DX」の4つの分野を設定します。来場者の持つ課題解決ニーズに応える製品・サービスを直接アピールすることができます。な企業が集まることで、業種を超えた新たな出会い、新たなビジネスチャンスの獲得を支援します。
2. リアル展とオンライン展のハイブリッド開催
本展示会ではオンライン会場をご用意し、リアル展示とのハイブリッド形式で開催します。 オンライン会場では、リアル展示の開催前に来場者へ出展情報(製品・サービス・資料)を提供することで、当日開催にスムーズな商談が可能となります。遠方でリアル展示へお越しになれない来場者、リアル展示会期中に来場する時間が確保できない来場者などからのアクセスも実現します。
3. 東京商工会議所のネットワークを主体とした広報活動
地域総合経済団体として、8万件超の会員を有する東京商工会議所のスケールメリットを活かすとともに、本部・23支部のあらゆるチャネルを活用した広報活動を実施します。や地域経済団体、金融機関など多様なネットワークも活用し、ビジネスマッチングの最大化・最適化を目指します。
4.充実した主催者企画
本展では以下の企画を予定しております。
・主催者企画『ビジネスチャンス商談会』・特別展示ブース(体験コーナー)・ラリークイズ・ITツール・サービス相談会「“ぴったり”マッチング」
5. 初出展の方も安心の出展者フォロー
参加者を対象とした説明会を10月中旬に開催予定です。 説明会では展示会効果の最大化に向けて、専門家による展示会セミナーを実施するほか、出展者同士の交流会も予定しあります。
名称:第3回 東京ビジネスチャンスEXPO
会期:リアル展:2023年12月6日(水) 12月7日(木) 10:00~17:00 2日間
オンライン展:2023年11月27日(月) ~ 12月11日(月) 15日間 ※オンライン展詳細は本日公開予定です
開催場所:東京ビッグサイト東1ホール
主催:東京商工会議所
共催:株式会社東京ビッグサイト
後援予定:東京都商工会議所連合会/東京都商工会連合会/公益財団法人東京都中小企業振興公社/公益財団法人東京観光財団/一般社団法人東京都信用金庫協会/一般社団法人東京都信用組合協会/東京信用保証協会/株式会社日本政策金融公庫/一般社団法人東京都中小企業診断士協会/日本小売業協会/一般社団法人全国スーパーマーケット協会
対象分野:フード、ライフスタイル、ものづくり、サービス・DX
展示規模:280企業、団体
来場対象:フード、ライフスタイル、ものづくり、サービス・DX等
入場者数:10,000名(予定、オンライン含む)
入場料:無料(登録制)
社名:コードレステクノロジー株式会社
本社所在地:東京都千代⽥区神⽥錦町2-9 大新ビル509
代表取締役:猿谷 吉行
内容事業:【Photolize】サービスの開発・販売・運営
設立: 2020年4月1日
HP:https://codeless-tech.com/
ビジョン:「インターフェースを最適化して世界中を元気に」
ミッション:「楽にしよう。」
多くの現場を経験してきて、ITの利用が苦手なユーザーがひと目見て「自分もできる」とは、
システム的に考えると重要なことと考えます。人は「できる」と思われるなら「やる気」が出てきます。
Photolizeのように簡単なシステムは「働く人を元気にする」ことができると考えています。
「お問い合わせ」はHP下部より、お気軽にご連絡下さい。
ビジネス特集 “10兆円”大学ファンドの船出 日本の大学衰退を救えるか | 教育
「研究費で、ボールペンが買えない」ある大学講師のツイッター上の投稿が、大きな反響を呼んだのは4年前。しかし、その後も国際的な競争の中、日本の大学の存在感は低下の一途をたどっている。そうした現状を打開しようと、政府が10兆円規模の「大学ファンド」を設立する。その運用益で、研究インフラの整備などの資金を捻出するのがねらいだ。このため「年間4%超」という高い運用目標を掲げるが、一方で失敗すれば公的な資金が失われるリスクもある。成算はあるのか?運用責任者に聞いた。(経済部記者 宮本雄太郎)
減る博士、論文シェアも低下
日本の大学を取り巻く環境は厳しい。大学の運営費交付金などが含まれる「科学技術予算」は、この20年近くでほぼ横ばいだ。およそ1.3倍となったアメリカはもちろん、8倍以上に増えた中国に大きく水をあけられた。ドイツに抜かれ、韓国にも追い上げられている。
予算規模の停滞は、研究力の衰退につながっているという指摘が多い。研究力を示す指標の一つ、「被引用論文数のシェア」をみると、2000年代に入ってから日本が低下を続ける一方、中国はめざましい勢いで上昇している。
研究開発の担い手となる博士号の取得者の数を見ても、日本はじわじわ減少している。アメリカや中国が大きく増加しているほか、イギリス・ドイツ・韓国も増加傾向にあるのとは対照的だ。博士号取得者の就職先が見つからない“ポスドク問題”や、海外では免除されることも多い博士過程の授業料の高さなどが、日本の特異な状況の原因と指摘されている。
政府主導の10兆円ファンド
危機感を抱いた政府が目を付けたのが、「大学ファンド」だ。アメリカでは、ハーバードやイェール、スタンフォードといった名門大学が数兆円規模の運用を行う基金を持ち、運用益を研究開発費や研究者の待遇改善などに充てている。ハーバード大学は2018年度の運用益が2000億円にも達し、大学の収入全体の35%を占めた。
日本でも、東京大学をはじめ一部の国立大や私大で基金の運用が始まっているが、その規模は数十億から数百億円程度と、規模が小さい。このため、政府が公費を元手に運用を行い、先進的な取り組みを行う大学に優先的に資金を配分しようと、ファンドの設立を決めた。元手は昨年度の補正予算や、国債で調達される財政投融資。運用資金は4兆5000億円から始まるが、近いうちに10兆円規模に拡大される方針だ。「世界的に見ても、類を見ない規模の大学ファンド」(政府関係者)となる。
その運用責任者に就任したのが、喜田昌和氏だ。喜田氏は、62兆円の資産を市場で運用する農林中央金庫の元常務で、株式や債券などを幅広く運用してきた。公的な資金が元手となるファンドだけに、その肩には期待と重圧がのしかかる。どのような戦略で臨むのか、喜田氏に聞いた。
運用目標は「4%超」
政府は7月下旬、ファンドの運用目標を「4.38%」と定めた。年間3000億円(3%)を大学側に配分し、長期物価上昇率(1.38%)も足し上げた数字だ。これは、年金積立金を運用する政府系ファンドのGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が定める4.0%より高い。そのため、大学ファンドが運用する資産の振り分けは、値動きの大きい株式の割合を65%まで引き上げることが認められた。
Q:「4.38%」は高い目標では?A:リターンの水準自体は、許容されたリスク量の範囲で過度に野心的だとは思わない。ただ、トレンドとしてグローバルな成長率は落ち、金利が上がりにくい環境になっているので、従来よりリターンが出にくいことは覚悟している。キーワードは、“局面に応じてポートフォリオ(運用資産の組み合わせ)を変えていくこと”。過度にリスクを取ることはないが、慎重になりすぎると運用目標は達成できない。調整局面でのリスクマネジメントが一番重要になるが、逡巡せずにやっていく。最初の頃は保守的になるかもしれないが、一方でPE(未上場株)や不動産などオルタナティブ投資(上場株式や債券以外での運用)も積極的に組み入れる。それぞれの資産運用で強みを持つコアメンバーをなるべく早く集め、年内には運用チームの目鼻をつけたい。
Q:運用益を大学側に還元する時期は?A:5年というのが一つのめど。このファンドの最大のリスク(懸念)が、大学側に運用益を配分できないこと。また、一度配分が始まったら、来年は出さなくてもいいだろうというのはあり得ない。安定的に配分できる軌道にいかにのせるかが、私のミッションだ。
Q:収益がマイナスとなるリスクもある。どう対処する?A:債券:株式=35:65という定められたリスクの上限の中で、柔軟に資産構成を変えていく。(運用資産の)評価損益のぶれは必ず対峙しなければいけないわけで、まずは利回りが確定している債券や社債、配当が期待される株式などを中心に、収益をためていくことを強く意識する。また、対外的に、こういう局面なのでこういう投資をしたんだということを、根拠を持って開示して、説明責任を果たすことに尽きる。
Q:海外では大学みずからがファンド運営の主体になっている。日本で政府系ファンドが主導する意義とは?A:ファンド自体が主役となるのではなく、日本全体の研究開発という主業がある中で、運用はその助成を行うエンジンだ。まずは他事考慮なくリターンを上げることが目標だが、願わくば投資の高度化、理論的なノウハウや体制づくりを図って、それぞれの大学が自ら資金を運用するためのモデルとなりたい。
「大学ファンド」は、今年度中に運用を始める。国が毎年大学に配る運営費交付金は全体で1兆円程度。もくろみどおりに、その3割に相当する金額を毎年、安定的に配分することができれば、大学の研究環境や研究者の待遇改善につながると期待される。一方で、運用で大きな損失を被れば、大学の競争力を高める方策も失う。巨大ファンドは、重い使命を背負って船出することになる。
経済部記者宮本雄太郎平成22年入局札幌局を経て経済部、現在金融業界を担当
テレビ東京『WBS(ワールドビジネスサテライト)』で『KAITRY(カイトリー)』が紹介されました | NEWSCAST
株式会社プロパティテクノロジーズ(以下「当社」)が運営している不動産AI査定サービス『KAITRY(カイトリー)』が、2024年12月26日(木)放送のテレビ東京『WBS(ワールドビジネスサテライト)』で紹介されたことをお知らせします。【マンションの「実家じまい」対応は?】2025年には団塊の世代が後期高齢者となる中で、「実家じまい」というテーマが注目されています。本特集では、当社代表・濱中雄大、CTO・金子健哉がインタビューを受け、当社が提供する不動産AI査定サービス『KAITRY(カイトリー)』の活用法や仕組み、そして実際に『KAITRY』を活用して「 「実家じまい」と言われた方への取材内容が取り上げられました。▼視聴はこちらからテレビBIZ(会員限定)TVer(11分4秒から)▼「実家じまい」について触れられている下記の記事も、あわせてご覧ください。■『KAITRY(カイトリー)』について『KAITRY』は、「住み替えを、もっと気軽に。もっと楽しく。」をコンセプトとした日本最大級のiBuyer(アイバイヤー)プラットフォームです。ユーザーは、最短5秒のAI査定によって、PC(パソコン)やスマホ、タブレットなどいつでもどこでも自分のマンションがいくらで売却できるか確認できます。 売却依頼から最短3日で現金化も可能です。また『KAITRYリノベ物件購入』ページでは、当社グループが自主販売主として注目している全国のリノベ済マンションを掲載しており、直接購入いただくことも可能です。住み替えをサポートしています。■株式会社property technology(プロパティ・テクノロジーズ)について「あなたの可能性を解き放ちましょう。年間33,000件超の不動産価格査定実績やグループ成立約12,000戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル(住まい)×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向けて、手軽でユーザーにとって利便性の高い不動産取引を提供しています。
<会社概要>会社名:株式会社プロパティテクノロジーズ代表者:代表取締役社長 濱中 雄大URL:https://pptc.co.jp/本社:東京都渋谷区渋谷3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階設立:2020年11月16日上場:東京証券取引所グロース市場(5527)画像・ファイル一覧一括ダウンロード
未来のビジネスリーダーが集結!「第4回ビジネスプランコンテスト 東京大会」を開催【東京ビジネス・アカデミー】 | 学校法人 21世紀アカデメイアのプレスリリース
学校法人21世紀アカデメイア(学長:田坂広志、本部:東京都千代田区)のビジネス専門学校 東京ビジネス・アカデミー(校長:稲場央人、東京都渋谷区)は、10月2日(水)に、 「21世紀アカデメイア 第4回ビジネスプランコンテスト全国大会 東京大会」を開催しました。
ビジネスデザイン学科から6チーム、経営学科から8チームがエントリーし、各学科より選抜されたチームにて実施。
東京大会を勝ち抜いた2チームが、10月14日(月)に開催される全国大会に出場します。
本作のポイント
①日々の疑問から考えるアイデアを昇華した、ビジネスプランを競い合うコンテストです。新規性・社会的意義・成長性・実現可能性などの観点から競い合いました。
②学生にとっては、プロフェッショナルとして活躍するために必要な創造的なコミュニケーション力、創発的なプロジェクト力を実学で学ぶ機会。
③新しい価値や仕組みを創造する力を学ぶビジネスデザイン学科と、高度な資格と成功する経営学を身につける経営学科の学生が参加します。フェムテックや高齢化社会の課題解決をテーマにしたビジネスプランが、全国大会の切符を勝ち取りました。
受賞チーム
「女性向けヘルスケアアプリ」(ビジネスデザイン学科2年生)
「老後に楽しみを」(ビジネスデザイン学科1年生)
ビジネスデザイン学科は、実体験や複雑化する社会の中にある課題を考えて、今までなかった新しいビジネスの事業計画を発表しました。
経営学科は、経済理論や経営戦略、マネジメント論の知識から、独自の起業計画を立てて、それぞれの学科の特性を話題にしたプレゼンテーションが盛んに行われました。
東京大会を勝ち抜いた学生の声
普段は経営学科のプレゼンテーションを聞くことはないので、数値データや資金面まで綿密に考えられている資料を見てビジネスデザイン学科とのアプローチの違いを感じてとても勉強になりました。
全国大会まであと1週間あるので、リフレクションでいただいた意見をもとに調整して臨みたいと思います。
「もっとこうしたらいいな」とか「私ならこうするな」とか考えられるのが、ビジネスプランコンテストの本物だと感じました。
全国大会では、選ばれなかったチームの気持ちもブリッジして頑張りたいと思いましたし、姉妹校のみなさんがどんなプランを考えているのかプレゼンテーションが楽しみです。
全国大会概要
上記の2チームは、10月14日(月)に行われる全国大会に進出します。
■名称21世紀アカデメイア 第4回ビジネスプランコンテスト全国大会
■開催日10月14日(月)
■会場大阪ビジネス・アカデミー
〔アクセス〕https://www.obc.ac.jp/access/
参加対象校
21世紀アカデメイアグループ
東京ビジネス・アカデミー
名古屋ビジネス・アカデミー
大阪ビジネス・アカデミー
福岡ビジネス・アカデミー
東京ビジネス・アカデミーについて
7年連続就職率100%*!「専門スキル」+「ビジネススキル」を身につける!
ペット・動物看護・スポーツ・ファッション・フラワー・経営・ビジネスデザイン・AI・IT・オフィス。
多様な10分野である程度の目指す専門スキルを伸ばすだけでなく、社会で活躍する上で本当に求められるコミュニケーション力・ビジネスマナー・PCスキルといった「社会人基礎力」の育成で、社会で即戦力となる力を身につける、代々木駅徒歩0分のビジネス総合校です。
クラス担任×就職活動担当教員×業界で活躍する「現役講師陣」「OB/OG」の構わないサポートでミスマッチのない就職満足度の充実をめざします。
※就職希望者対象実績
■東京ビジネス・アカデミー公式ページ
https://www.tsb-yyg.ac.jp/
■東京ビジネス・アカデミー公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tsb_yyg/reels/?hl=ja
■お問い合わせ先
東京ビジネス・アカデミー広報部 松本・関
メール:[email protected]
TEL:03-3370-2244
第4次産業⾰命が急速に発展し、ロボティクスや⼈⼯知能(AI)が社会に進む時代には、⼈材に求められる条件が根本から変わっていきます。
その結果、ただ⼤学で「知識」を学んだだけの⼈材は、⽣き残りません。
また、ただ専⾨学校で「技能」を⾝につけるだけの⼈材は、活躍できません。
これからの時代、職場や企業、業界や社会において優れたリーダーシップを発揮して活躍する⼈材は、⼈間だけが活躍できる⾼度な能⼒である「5つのプロフェッショナル⼒」を⾝につけた⼈材です。
21世紀アカデメイアでは、この人材を「ファイブ・スター・プロフェッショナル」(Five Stars Professional)と考え、その育成のための独⾃の実践体験的なカリキュラム、「セブン・ステップ・カリキュラム」を開発し、すべての学⽣に提供しています。
ビジネス特集 線路跡に温泉? シモキタ式のまちづくりとは | 新型コロナ 経済影響
演劇や古着の街として知られる、東京・下北沢、通称「シモキタ」。「開かずの踏切」に象徴される雑多な街並みが魅力でしたが、近年は鉄道の地下化にともなって商業施設やホテル、温泉旅館など新しいスポットが次々と誕生し、駅前の風景は様変わりしています。シモキタの大胆な変貌は、いったいどう進められてきたのか。そしてこれからのシモキタは、どう変わっていくのでしょうか。(経済部記者 真方健太朗)
シモキタはどう変わった?
小田急線と京王井の頭線が交差する東京・世田谷区の下北沢駅。改札を出て新宿方面に5分ほど歩くと、従来のシモキタらしからぬ建物が見えてきます。白を基調とした外観。周囲には木々が植えられ、海外の高級住宅街のような雰囲気。8年前に地下化された鉄道の線路の跡地に、ことし6月に開業した商業施設です。開発した鉄道会社の担当課長、橋本崇さんに現場を案内してもらいました。
記者「従来のシモキタのイメージとはずいぶん違いますよね?」橋本さん「いえいえ、シモキタらしい、店主の顔が見える施設なんですよ」
この施設は24の店が入る予定ですが、雑貨店に古着店、カレー店などほとんどが個人商店です。近年、街にチェーン店が増えてきて下北沢の魅力が失われつつあるという地域の声を反映させました。
線路の跡地には、このほかにも、箱根から温泉を運んでくる温泉旅館や、学生や若手の社会人が共に学びながら生活するユニークな施設など、ちょっと変わったスポットが並びます。これらは、開発主体の鉄道会社と、地域の住民とがアイデアを出しながら、「支援型開発」というコンセプトのもとで整備を進めてきました。
橋本さん「住民のみなさんが街で実現したいことを鉄道会社が支援する。これがシモキタ式のまちづくりだと思っています」
かつては激しい反対運動
下北沢のまちづくりは、長い対立の歴史でもあります。かつて激しい反対運動が行われ、住民を二分する議論になっていました。小田急線の地下化が決まった2003年頃。地下化と同時に進められようとしていた世田谷区による駅前の開発計画に批判が集まりました。
下北沢駅は、当時も今も、車が通る幹線道路からは奥まった場所にあり、マイカーやタクシーが近づくことはほとんどありません。当時の開発計画は、駅前にバスのロータリーや幅26メートルの道路を新たに建設するというもの。これによって車は通りやすくなりますが、劇場や一部の飲食店は立ち退きが必要でした。
当時、反対運動の中心だった下平憲治さんとミュージシャンの六弦詩人義家さんに話を聞きました。下平さんは2003年に住民団体の「Save the 下北沢」を立ち上げ、デモや行政への要望活動を行ってきました。六弦詩人義家さんは、この問題について音楽や映画を通じて発信するイベント「SHIMOKITA VOICE」の実行委員長を務めています。リリー・フランキーさんや柄本明さんなど演劇界の著名人も反対運動に賛同しました。
記者2人は、なぜ開発事業に反対したのですか?下平さん「シモキタは自由に歩き回れるのが魅力。道路ができたら街が壊されてしまう」六弦詩人義家さん「人が集まってくるかっこいい街がシモキタです。路地裏文化は守っていきたい」
一方で、反対運動と距離を置く住民も多くいました。下北沢は狭い路地の雰囲気が魅力ですが、火事や大地震などの災害時に消防車などの緊急車両が近づけないおそれがあります。また、鉄道の線路が街を南北に分断し、「開かずの踏切」による混雑も課題でした。6つの商店街で作る下北沢商店連合会の会長を務める柏雅康さんは、賛成と反対で街が二分され、将来の方向性がなかなか決まらないことで、閉塞感が漂っていたと話しています。
柏さん「開発するのかしないのか、早く決めないとなにも身動きがとれないという気持ちでした」
街の将来を決める開発事業に住民の声が届かない。住民の不安は、小田急電鉄の線路跡地の開発にも向けられました。2013年に線路の地下移設が完了し、東北沢、下北沢、世田谷代田の3つの駅にまたがる広大な空き地をどうするのかが焦点になりました。2014年ごろから、跡地利用を考える行政の説明会が頻繁に開かれるようになりましたが、開発の主体である小田急電鉄の担当者は顔は見せないままでした。地下工事完了後、6年間も具体的な計画が決まらなかったのです。
対立から協働へ
2017年に線路跡地開発の担当課長になったのが、冒頭で案内してくれた橋本さんです。計画が進まない事態を打開しようと、住民が主催するまちづくりの会議に参加しました。当時、会社として公式に地域の住民の前に立つのは初めてのことでした。激しい反対運動を行ってきた住民など50人あまりを前に、どんな批判を浴びせられるのか不安だったと言います。
しかし、意外なことに住民からはまちづくりへの具体的な提言が相次ぎました。「みんなが気持ちよく歩ける緑地を作ろう」「シモキタには宿泊できる場所がないから旅館が必要ではないか」「下北沢の住民はただ反対しているのではない。まちづくりでやりたいことがあるのだ」ーーー橋本さんは、こう確信し、住民との対話を深めました。反対運動を先導してきた下平さんとも街の未来を語り合うようになりました。そして商店街が開く、流鏑馬や盆踊りなどのイベントにも会社として積極的に協力するようになりました。こうした中から、住民の声を開発側が後押しする「支援型開発」のコンセプトが生まれ、対立から協働へと舵が切られたのです。冒頭で紹介した商業施設や温泉旅館はこうした住民の声から生まれました。
シモキタ式のまちづくりとは
今回取材した人たちが共通して語っていたのは、街の個性が失われることへの危機感。日本では、駅前の開発で大きなビルができてチェーン店が入る「便利だけど似たような街」が多く見られます。シモキタに関わる人たちは、「似たような街」と同じにならないまちづくりをめざして、努力を続けたいと話します。
反対運動の中心だった下平さん「シモキタは壮大なる社会実験の場です。成熟した住民が声を上げて人を惹きつける街にし続けられるか挑戦したい」下北沢商店連合会の柏さん「シモキタはおもちゃ箱のような街。これを賛成派も反対派もなく住民で連携して守っていきたい」
一方で、鉄道会社の橋本さんは、新型コロナウイルスの影響で、鉄道会社が通勤や通学で稼ぐ時代は終わりを迎えた、まちづくりの転換点が10年早まったと指摘します。「電車に乗らなくても住民が住み続けたいと思う街にして、それに鉄道会社が貢献することが重要です。シモキタはそういう意味では最も先進的な街です」下北沢の開発は、これですべて丸く収まったわけではありません。世田谷区や小田急電鉄の開発をめぐって、反対派の住民との議論は、今も続いています。住民が自分たちの将来の姿を積極的に考える「シモキタ式のまちづくり」は、これからの下北沢をどう変えていくのでしょうか。
経済部記者真方 健太朗帯広局、高松局、広島局を経て、現在国土交通省を担当
日銀 利上げ0.5%に 賃上げ期待|テレ東BIZ(テレビ東京ビジネスオンデマンド)
日銀は24日までの金融政策決定会合で、現状0.25 %程度としている政策金利を、0.5 %程度に引き上げました。日銀植田総裁「わが国の経済物価が、これまで示してきた見通しにおおむね沿って推移していて、先行き見通しが実現していく確度が高まってきていると判断した」 2025 年の春闘で高い水準の賃上げが期待できることなどや、アメリカのトランプ新政権についても、様々な不確実性は意識されているものの、「市場は全体として落ち着いている」と指摘しました。また、最近のコメの価格の上昇や、輸入物価の上振れによって2024年2025年年度の物価見通しを上方修正し、「金融緩和度合いの調整が適切と判断した」と話しました。今後の利上げについては「ペースやタイミングについて予断を持っていない」として、それぞれの会合ごとにデータを分析し、判断していく姿勢を強調しました。
【来場登録 開始!】日本最大級* DX・ビジネス変革のための総合展/サッポロ、富士通、マイクロソフト、Twitter Japanなど特別講演も40本併催 | NEWSCAST
2月東京ビッグサイトで開催! 〜DX・経営課題解決のための総合展〜
...
最優秀賞は「時を自在にデザインする真鍮ブランドの提案」に決定。2023年度 東京ビジネスデザインアワード 最終審査結果 – デザイン情報サイト[JDN]
「東京ビジネスデザインアワード」の提案最終審査が2月8日に行われ、2023年度の最優秀賞1件と優秀賞2件が発表されました。
東京ビジネスデザインアワードは、東京都内の中小企業を対象に事業支援・新規市場開拓を目的として毎年実施されるコンペティション。企業が有する製造加工技術や素材ノウハウなどを「テーマ」として募集し、それらを活用するした新たなビジネスプランや新規用途開発のアイデアなどをデザイナーから募集し、両者のマッチングにより事業を推進していきます。
今年度は11のテーマと提案がマッチし「テーマ賞」を受賞しました。2月8日の最終審査ではテーマ賞を受賞したデザイナーがプレゼンテーションに臨んだ。
「最優秀賞」にたのしみは、株式会社富士産業・榎本清孝(アートディレクター/プランナー/株式会社トムテ)・村上麻衣子(デザイナー/株式会社トムテ)による「時を自由にデザインする真鍮ブランドの提案」 」だ。
最優秀賞「時を自由にデザインする真鍮ブランドの提案」。 企業テーマは、職人技で古美色を再現する「硫化燻し加工技術」。 これに対し、「企業の高い技術力とデザインの力」で、真鍮に新たな価値を与え事業拡大していくブランドプロジェクトの提案」が起きなかった
デザイナーを代表して登壇した榎本清孝は「自分自身はグラフィックデザインの人間だが、今回のプロダクトをグラフィックデザイナーとの協議、利益につながっていくかが今後試されると思っているので、頑張っていきたい」 」と話しました。
また、「優秀賞」を受賞したのは、有限会社オクギ製作所・千龍馬(デザイナー)・梅村隼多(デザイナー)による「ワイヤーカット放電加工を相談したアクセサリーブランドの提案」と、株式会社江北ゴム製作所・土井智喜(デザイナー/soell株式会社)による「自然に優しいゴムと廃棄材を融合させたプロダクトブランドの構築」の2件。
審査委員長を務めたバイヤー/株式会社メソッド 代表取締役の山田遊は、テーマ賞を受賞した11組のプレゼンには、実現性が高く、売れるだろう想像できるものが複数あったとし以下のようにコメントした。
「今回のプレゼンテーションにも『共創』というキーワードがあったが、これは経営者・デザイナーだけでなく顧客や審査員も含めた、ステークホルダー全員にわかれないこと。サービスやプロダクト全体を一緒につくる人や購入者すらも、共創する仲間であるという認識が今後必要になるのではないか―とりあえず購入・消費の形に社会の流れが変わっているように感じられる。思っていただきたい」
実現に向けて、具体的な協働が開始される受賞計画の今後の展開に注目したい。
https://www.tokyo-design.ne.jp/award.html












![最優秀賞は「時を自在にデザインする真鍮ブランドの提案」に決定。2023年度 東京ビジネスデザインアワード 最終審査結果 – デザイン情報サイト[JDN] 最優秀賞は「時を自在にデザインする真鍮ブランドの提案」に決定。2023年度 東京ビジネスデザインアワード 最終審査結果 – デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/02/f64307898d45390c0f8d6d272527cd2b.jpg)